Vol. 1 水野弘之氏(日立京大ラボ所長)前編
2023.01.30
2016年6月、日立製作所と京都大学は、「ヒトと文化の理解に基づく基礎と学理の探究」を推進するため、共同研究部門として「日立京大ラボ」を設立。双方の研究者や学生が一体となり、社会課題の解決やQuality of Life 向上に向けたイノベーションの創出に取り組んでいます。
今回は、現在ラボ長を務める水野弘之氏に、ラボ発足の経緯をはじめ、会社の危機を経験したからこそ挑戦できたという、分野を超えた新たな産学連携のあり方についてお話を伺いました。
(藤川二葉=聞き手/水野良美=構成)
水野弘之(みずの・ひろゆき)
株式会社 日立製作所研究開発グループ基礎研究センタ主管研究長 兼 日立京大ラボ長
1993年日立製作所入社。2002年から 2003年まで米国スタンフォード大学客員研究員。工学博士。米国電気電子学会(IEEE)フェロー。現在は、2020年にプログラムマネージャーに就任したムーンショット型研究開発事業でのシリコン量子コンピュータの研究開発と、人文社会科学・神経科学・人工知能を融合した研究テーマに取り組む。日立京大ラボでは、「ヒトと文化の理解に基づく基礎と学理の探究」をテーマとして、京都大学の有識者・研究者、学生などと共に文理融合のもと新たな社会イノベーションの研究を進めている。
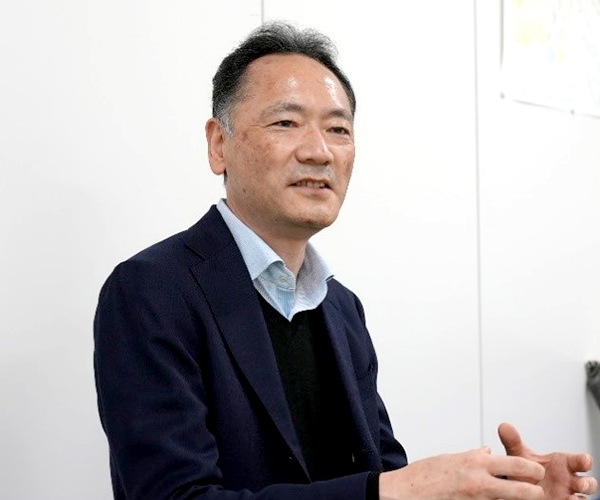
研究テーマに見る日立京大ラボの独自性
——日立京大ラボは「ヒトと文化の理解に基づく基礎と学理の探究」をテーマにされています。どのような期待があり、このテーマを設定されたのでしょうか。また、日立は同様のラボを国内外に有しておられますが、国内における他大学のラボ(日立東大ラボ、日立北大ラボ)との比較も交えてお聞かせください。
まずは、水野さんにおたずねする前に、日立京大ラボ設立当初からご在籍の嶺竜治さん(主任研究員兼ラボ長代行、京都大学オープンイノベーション機構特定准教授)にお話を伺います。
嶺 日立京大ラボは、京都大学と日立の協創によって未来の社会課題を洞察し、ヒトやモノが織りなす社会や文化に関する基礎と学理の探究を通じて、社会課題の解決と経済発展を両立する独創的なイノベーションの創出を目指して設立されました。
とくに、「人が人であるがゆえに起きる社会課題」、つまり、そもそも人は合理的な生き物ではない、という事実を出発点として、それゆえに生じる課題を探究することに主眼を置いています。日立京大ラボのテーマである「ヒトと文化の理解に基づく基礎と学理の探究」に「ヒト」という字が入っているのはそのためです。
いっぽう、日立東大ラボでは、従来の課題解決型産学連携から発想を転換し、日本政府が提唱する「超スマート社会(Society 5.0)」(*1)の実現に向け、ビジョンを創生・発信し、その実現に向けた課題解決に取り組んでいます。日立北大ラボは、北海道が直面する少子高齢化や人口減少、地域経済の低迷、地球温暖化などの社会課題解決に実践的に取り組んでいます。日本の他の地域に先駆けて、こうした社会課題の解決に挑戦していくことで、「超スマート社会」の実現のプロセスを北海道から発信している、とも言えるでしょう。
それらと比較すると、日立京大ラボには産学連携の方法においても、他にはない特徴があります。通常の産学連携のスタイルでは、製品やソリューションを実現するにあたり、大学の先生方の知見や知識をお借りしようと、メーカー側が大学に課題を持ち込むパターンが多い。対して、日立京大ラボでは、先生方と一緒に課題を探すところから始めます。当ラボの京大側の呼び名である「日立未来課題探索共同研究部門」には、そういった思いも込められているのです。
ラボ発足の経緯を振り返って
——水野さんは、当時東京の本社にいらしたわけですが、ラボ設立当初、東京ではどのような動きがあったのでしょうか?
水野 その頃は、ちょうど全体的に研究開発グループの組織を大きく変えた時期でもありました。フロントのお客様との接点をより充実させた組織がまず整備され、それに付随するかたちで大学との関係も見直すべく、日立の基礎研究センタ(*2)が大学内に組み込んだエンベデッドラボを構築しました。
もちろん、従来から大学との連携は行っていましたが、当時はお客様との関係を見直すのと同時に、アカデミア集団との関係の見直しも図ろうということで、まずは 3 つ、京都大学、東京大学、そして北海道大学でエンベデッドラボを設立したのです。今後、どういう風に大学とお付き合いし、新たな関係を築いていけばよいのか——3 つのラボは、そうしたことを考えるために作られた組織として理解していただければよいと思います。
——嶺さんは以前お会いしたとき、日立製作所の内部で、京都大学と組むのであれば人文社会科学系の先生方と一緒にやらなければ、とのご意見があったとおっしゃっていましたが、もしよろしければそのあたりについて、もう少し詳しくお聞かせいただけますか?
嶺 ラボが設立された当初は、情報系や工学系の先生方ともご一緒する機会があったのですが、お互いの持ち分を生かすかたちでの連携となると、双方の領域が重なりすぎてしまい、なかなか難しい面があったように思います。例えば「情報×情報」となると、専門が近すぎるため、あまり社会的にインパクトがあるものは生み出せない。よりよい情報技術やアルゴリズムは生まれるかもしれませんが、そこで止まってしまうのです。
いっぽう、文系の先生方の場合は「社会をこう変えたい」「社会はこうあるべきだ」といったビジョンがあり、そもそも価値観って何だろう、と前提を問い直すところから議論が始まる。そこで、われわれがその問いを共有し、課題解決の方法を提供できれば、一緒にどんどん前へと研究を進めていけるわけですね。
水野 ポイントは理系か文系か、というよりも、ひょっとしたらお互いの専門領域の重なり具合など、人による部分も大きいのかもしれません。

技術への向き合い方を問い直す
——本日はもうお一人、ラボ員の加藤猛さん(京都大学オープンイノベーション機構特定准教授)にもオンラインで同席いただいているのですが、加藤さんは当時を振り返ってみて、いかがでしょうか?
加藤 わたしの場合は、ある日突然、いきなり会社から「京都に行ってこい」と言われまして(笑)。それはともかく、日立京大ラボの設立以前から、水野さんも含め、先々の社会のあり方を根本から考え直すため、当時社内ではよく生物システム論や社会システム論などに関する議論をしていましたね。これから先は、単純に技術だけではうまくいかなくなるはずだ、と考えていたためです。
当時から、われわれはどちらかというと「はずれ者」ばっかりでしたので(笑)。好調な技術を淡々と推し進めるだけでは済まない立場と言いますか。けれども今振り返ってみると、ある意味、むしろはずれていたことがよかったのかもしれません。そもそもこのままでよいのか、と考えるきっかけになりましたから。
水野 当時のそうした背景には、本来主軸であるはずの研究フィールド(半導体)が、日立のなかで事業的に注力しない分野になった、という事情がありました。いわゆる社内失業のような状態のなかで、次へ向けて変わっていかねばならないときに、ふと「これから何をしようか」から議論が始まり、世の中をもう一度俯瞰的に見直す作業を東京でやっていた。
つまり、加藤さんの言うとおり、本当にこの先も技術のことだけを考えていてよいのだろうか、と立ち止まり、先々の社会を見据えた根本的な議論にまで立ち返っていたのです。その後 2、3年、考え続けて悶々としているところに、日立京大ラボの構想が浮上し、現在に至っています。その意味では、京都に行く前から現在に通じる課題意識があったために、のちにお会いできた先生方との議論もスムースに進められたように思います。
社会イノベーション事業への挑戦
——これまでの日立京大ラボの成果は『BEYOND SMART LIFE:好奇心が駆動する社会』(日立京大ラボ編著、日本経済新聞出版、2020 年)にまとめられていますが、同書の受け取られ方についてはいかがでしょうか?
水野 ありがたいことに、とくに経営に深く関わっておられる方々から大きな関心を寄せていただいているように感じています。おそらく時代の先を考えようとされているのだと思いますが、そういうかたとであれば急に会話が成り立つようになるのです。このラボに来てくださる方々も、会長や社長クラスのかたが多いのは、そのためかもしれません。
嶺 本書の内容は、ここでの研究成果がいつ製品になり、いつ利益につながるのか、という話とは時間軸も異なり、より先を見据えたものになっているため、その点は必然的とも言えそうですね。この本は「社会イノベーション」について書かれていますが、それが意味するところは、今後の日本社会を覆うであろう「3 つの喪失(トリレンマ)」から脱出する 1 つの処方箋として、自分事として社会課題を捉え解決していく、ということなのです。
ここで言う「トリレンマ」とは、2050 年の日本社会が直面しうる社会課題の根源を探索した際、見出された根本的な問題としての3つの喪失——「信じるもの=未来」「頼るもの=国家」「やること=労働」の喪失——を指しています(*3)。
われわれが社会イノベーション事業をとおして伝えたいのは、この先、誰かが課題を解決してくれるとか、いずれテクノロジーが社会を便利なものにしてくれる、といった類の考えではありません。自分で技術を作るなり、社会の仕組みを作るなりして解決すれば、それがいずれは自分たちの幸せにつながる——目指すのはそういったイメージです。
水野 日立は、2009 年 3 月期に国内製造業としては過去最大の損失を計上したこともあり、以後、大がかりな構造改革を行うなかで、会社として何を目指していくべきかを抜本的に考え直す時期がありました。そのなかで、今この日立京大ラボで取り組んでいるような本質的な社会課題についても、ある程度近いところまでは議論していたわけです。
現在日立が取り組んでいる「社会イノベーション事業」はこの時期に生まれた言葉で、当時は世界的に見ても新しい言葉だったと思いますが、今やほとんどの会社が取り組んでいます。われわれが新しいことに挑戦できたのは、最悪の事態を経験したことで、自らを省みる時期があったおかげかもしれません。
哲学的思考法との出合い
——本書では、哲学系の先生方との相互作用について書かれた部分もたいへん興味深く拝読しました。先ほど嶺さんにも少しお話いただきましたが、改めて、そのあたりについてはいかがでしょうか。
加藤 やはり哲学系の先生方とご一緒すると、われわれとしては技術をめぐる議論の延長で当然のことを言っているつもりでも、そもそもの部分を問い直されるために、いつも議論の前提をひっくり返される。会社では、常に事業利益を上げることのみに注力するよう言われるわけですけれど、それでいいのかな、と考えさせられます。
例えば、政策提案 AI のプロジェクト(*4)などでご一緒した、公共政策と科学哲学がご専門の広井良典先生(京都大学人と社会の未来研究院教授)から、「東京一極集中で事業利益を吸い上げていると、地方の経済が回らないでしょう」と指摘されると、企業としてのあり方そのものを考え直さないといけない、と思わざるを得なくなる。
先生方との交流を通じて、根っこの部分から意識が変わってきていることは確かですね。技術の他にいろいろな見方や課題があること、営利ありきではなく世の中あっての企業であることを知れたことが、今のわれわれの立脚点になっています。
嶺 学会発表で接する機会がある工学や情報系の世界では、新しい方式やアルゴリズムを考えたり、計算スピードを上げて課題を解決したりすることがよくある研究のパターンなのですが、哲学系の先生方の場合は、新しい問いの発見それ自体が成果になると知って驚きました。
そうすると、「課題」自体についても再考を迫られるようになる。課題がないと研究テーマが生まれないと思ってしまいがちですが、それは真に解決すべき課題なのかどうか。「社会課題」という言葉自体も、本当はあまりよくないのかもしれません。ポイントは課題そのものにではなく、いかに課題の本質を捉え、適切な問いを立てられるかどうか、という点にあるのですね。
当初は、そのような考え方に慣れるまでが結構大変でした(笑)。けれども、人文社会科学分野との連携はわれわれにとってもメリットがあるし、先生方ご自身にとってもメリットがあるのではないかと思っています。
企業側の研究者にとっては、人文社会科学系の研究者と連携することによって、技術にとどまらない、広範で、多角的な検討が可能になります。また、社会課題の解決にとどまらず、課題の設定や価値の創生まで遡って検討することもできますし、まだ顕在化していない社会課題の気づきを得ることもできます。
いっぽう、人文社会科学系の研究者にとっては、当分野の研究で得られた知と、実社会の具体的ニーズのギャップを小さくできるというメリットがありそうです。また、より良き社会を作り出すパートナーとして企業と連携することで、人文社会科学系の研究成果が社会実装や社会実践につながっていくことでしょう。さらには、そうした連携を進めるなかで、当分野における新たな課題の発見につながっていく可能性もあるのではないでしょうか。
共に問いを立てて解決し、また新しい問いを見つけて解決し、考える——そうしたループがうまく成立しているように感じます。
脚注
*1 内閣府 総合科学技術・イノベーション会議
https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5honbun.pdf(アクセス日:2022年12月20日)
*2 2015 年、日立製作所の研究開発グループが、未来社会の課題解決に向けた研究開発を担うために設立した組織。あわせて、顧客協創をグローバルに推進する「社会イノベーション協創センタ」、AI やセンシング、ロボットやセキュリティなどの先端技術革新を推進する「テクノロジーイノベーションセンタ」が設置された。
*3 「3つの喪失(トリレンマ)」についての詳細は、日立京大ラボのプロジェクト「2050 年の社会課題の探索」を参照のこと。
https://www.hitachi.oi.kyoto-u.ac.jp/project/417/(アクセス日:2020年12月20日)
*4 日立京大ラボのAI(Artificial Intelligence:人工知能)技術を、京都大学で進めている持続可能な日本の未来の実現に向けた研究に適用することで、社会を数学モデルで表し、その未来をシミュレーションするシステムとしての活用が試みられた。
https://www.hitachi.oi.kyoto-u.ac.jp/project/145/(アクセス日:2022年12月20日)



