Vol. 3 小林傳司氏(大阪大学名誉教授、同COデザインセンター特任教授 兼 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 社会技術研究開発センター(RISTEX) センター長 前編
人と社会の未来研究院では、「学内での学際連携による総合知の創出」、「産業界や行政などの社会連携から創発する新たな研究の推進」、「人文社会科学の知見の学術的発信機能の拡充・強化」の三つの方針を掲げ、人文社会科学分野の研究力の底上げと、人文社会科学知財の国際的な活用・プレゼンスの向上に取り組んでいます。今回の社会連携インタビュー「この方に聴きました」では、JSTの社会技術研究開発センター(RISTEX)でセンター長を務める小林傳司氏に、RISTEXでの活動や人文社会科学の社会とのつながりのあり方についてお話を伺いました。
(聞き手:沼田英治特定教授、広井良典教授/取材補助:稲石奈津子、水野良美/構成:福田将矢)
小林傳司(こばやし・ただし)
大阪大学名誉教授、同COデザインセンター特任教授 兼 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 社会技術研究開発センター(RISTEX) センター長
1978年京都大学理学部卒業、1983年東京大学大学院理学系研究科博士課程単位取得退学。2005年大阪大学コミュニケーションデザイン・センター(CSCD)教授、2015年より大阪大学理事・副学長。2019年より科学技術振興機構(JST)科学技術研究開発センター(RISTEX)上席フェロー、2020年より大阪大学名誉教授、同COデザインセンター特任教授。2021年よりJST RISTEXセンター長。
専門は、科学哲学・科学技術社会論。著書に、『誰が科学技術について考えるのか コンセンサス会議という実験』名古屋大学出版会(2004)、『トランス・サイエンスの時代 科学技術と社会をつなぐ』NTT出版ライブラリーレゾナント(2007)など。
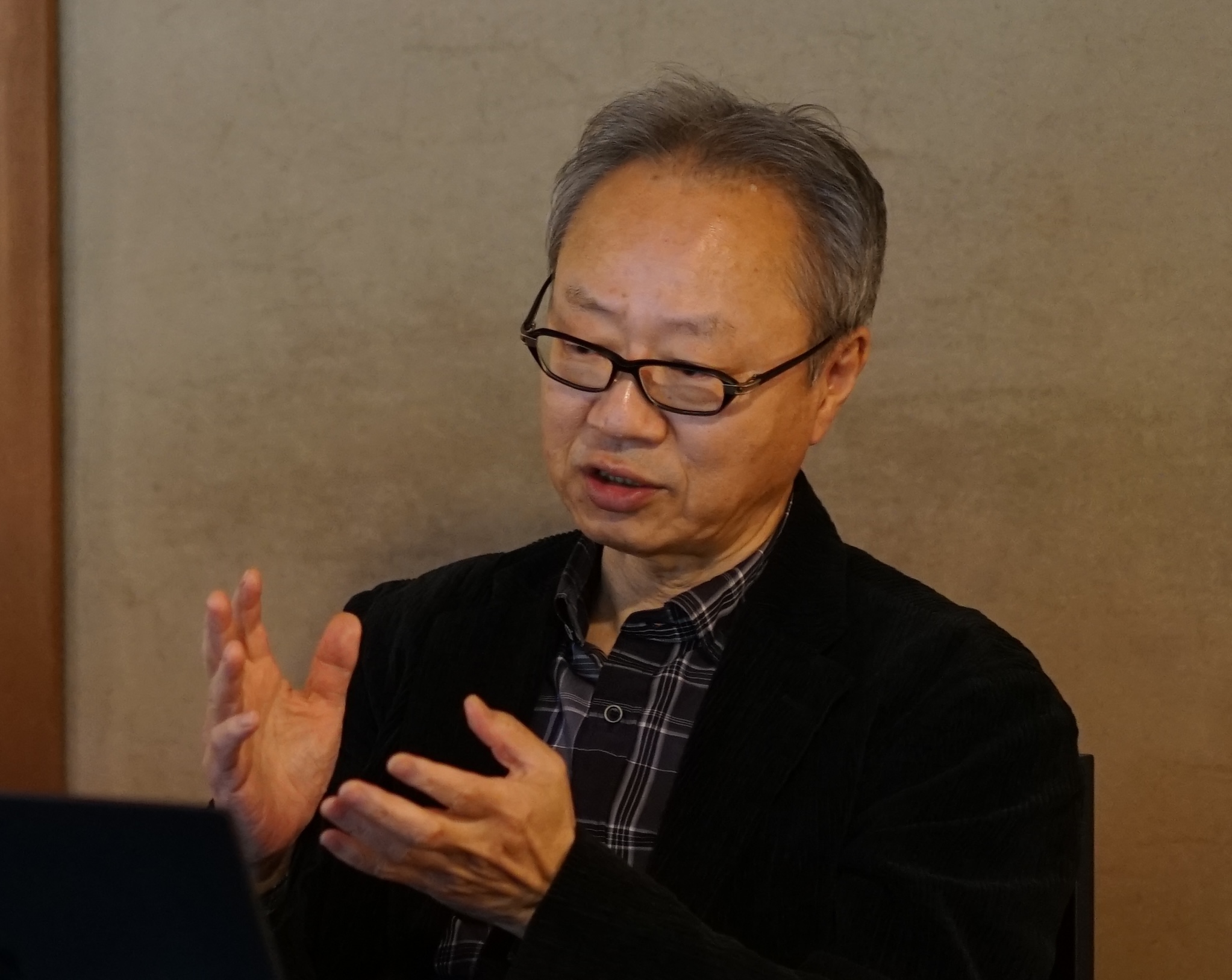
社会技術研究開発センターとは
沼田:小林さんはJSTの社会技術研究開発センターのセンター長をされていますが、これはどういったお仕事なのでしょうか。
小林:JSTとは科学技術振興機構といって、政府のもとで研究資金の提供をする機関です。基本的には理工系などの大型の研究に対する支援がメインですね。医薬系は日本医療研究開発機構(AMED)というところが管理しています。このJSTやAMEDというのはどちらかというとトップダウン型で、どういう研究を推進するかを決めて、研究者に応募してもらったのちに採用し、マネジメントを行いつつ研究をしてもらう、そういうスタイルです。私の所属している社会技術研究開発センターはこのJSTの中の組織です。このセンターの大きな特徴の一つは、解決が求められる社会的課題を探索したうえで、それに取り組む研究領域を設定し、その課題の解決に資する研究チームを作って応募してくださいという問題の立て方をするところです。社会的課題の解決には工学だけが関連するわけではないので、それに必要な学問であれば何を持ち込んでも構いません。ただし現場の当事者を巻き込んだ形でやってくださいねというメッセージを出したわけです。このセンターができた背景に関しては少し長くなりますが、順を追ってお話しようと思います。
20世紀末ごろに冷戦が終わると、21世紀の科学技術というのはどのような役割を果たすべきなのかということがいろんな方面で議論されました。特に冷戦期、軍事科学と基礎科学とがセットになって多くの投資が行われていたアメリカでは、冷戦後に軍事科学系の研究をどのように民営化していくかについて多くの議論がなされました。その中でアメリカはこれらの研究は人々の生活にも使えますよ、ということで経済のための科学という方向に舵を切りました。そのころは日本や韓国が軽武装路線のもと、軍事研究にはそれほど手を染めず、基礎研究への投資は薄くして応用・開発研究に力を入れていた時代だったので、軍事研究を中心に取り組んでいたアメリカはそれに対する危機感があったのかもしれません。
一方で日本はどうだったかというと、欧米諸国から「基礎研究ただ乗り」に関する批判を受けたことを踏まえ、「科学技術基本法」という法律において基礎研究に投資をする形での科学政策が打ち出されました。この法律に基づいて5年間の科学技術基本計画が策定されるのですが、その第一期や第二期では基礎研究の振興が強調されていますが、その後第三期、第四期からはイノベーションを中心とした議論に切り替わっていきます。これらを踏まえて科学技術基本法は2021年に「科学技術・イノベーション基本法」へと改正されました。このように、日本はアメリカなどと比べると少し違う経路を辿りましたが、どちらにしてもキーとなるのは経済的な発展に科学が貢献するというフレームです。ちなみに、この改正によって、従来法の範囲に含まれていなかった、人文社会科学系研究も扱うようになりました。
これに対し、1999年にハンガリーのブダペストで発表された「科学と科学的知識の利用に関する世界宣言(ブダペスト宣言)」では、全ての研究者が自分らの研究を社会に役立てるような方向に、新しく社会と契約を結んで舵を切っていくべきという主張が行われました。この背景として、1992年にリオデジャネイロで行われた国連環境開発会議(地球サミット)以降、地球環境問題がようやく国際的な議論の的となったことがあげられるかと思います。同時期のアメリカでも「科学と社会の新しい契約」に関する議論が出てきています。ブダペスト宣言では科学の役割として「知識のための科学、進歩のための科学」に加え、「開発のための科学」、「平和のための科学」、そして「社会における科学、社会のための科学」と定義しました。よく誤解されるのですが、知識のための科学が理学部、社会のための科学が工学部、というように振り分けるのではなく、あらゆる研究分野がこれらにまたがった感覚を持つべきだというメッセージが打ち出されたわけです。
日本ではこのブダペスト宣言の存在に加え、新たな研究のスタイルと研究資金を獲得するための切り口を模索していた科学技術庁の中での議論とがシンクロした結果、2000年に「社会技術開発センター」が設立されました。英語の名称はResearch Institute of Science and Technology for Society(以下RISTEX)です。最初に述べた通り、本センターでは解決が求められる社会的課題を探索したうえで、それに取り組む研究領域を設定し、その課題の解決に資する研究チームを作って応募してください、またその際のメンバーは分野を問わず現場の当事者を巻き込んだ形でやってもらいます、という方針をとっています。こういうわけで、よく文理融合をやっているのですね、と言われることがありますが、文理融合を目指したのではなく、ある社会的課題を解くために必要な研究をやろうとすると、結果的に文理融合になっていく、という言い方が正しいかと思います。当事者を巻き込むというのは今風に言うと、transdisciplinarity=超学際と呼ばれているものです。実は私はこの訳語が嫌いなので撲滅運動をやっているのですが(笑)。「超」というのが、この語の意味をきちんととらえていないように思うのです。
このように、RISTEXではある課題を設定し、それに関係する研究チームを作って応募してもらうということを繰り返してきました。JSTの中では人文社会科学の人が少なかったので違和感を覚える人もいるようですが、幸い最近は総合知や科学技術基本法改正のおかげもあり人文社会科学を重視しようという動きが出ているので、その雰囲気は和らいでいるようです。
広井:社会では今やっと総合知や文理融合という言葉が浸透してきていますが、2000年のRISTEXの設立はブダペスト宣言のあとかなり早い動きだったと言えるのではないでしょうか。
小林:おっしゃるとおりです。RISTEXとしては、社会的課題を解決するための課題と研究者の社会との関係を確立するというところを重視していて、それらが今の「科学技術社会論」のバックボーンとなっていると思います。こちらに関してはまた後ほどお話しようと思います。
理学から科学哲学へ
沼田:小林さんは京都大学の理学部出身ですが、大学院から科学哲学の道に進まれています。科学に対する姿勢の変遷についてお伺いしてもよろしいでしょうか。
小林:高校の頃は文学部に行くか理学部に行くかで迷っていました。当時、京都大学の理学部は霊長類研究のメッカであり、そういったことをやってみたいという思いから最終的に理学部に行くことにしました。しかし、入ってみると全国からそういうことをやりたい人が集まっていたこともあり、人並外れた強靭な体力を持っている人が多かったんです。私はあまりそういう体力もなかったですし、理学部の教育では実験をたっぷりとやらされるのですが、それが苦手で、私が触るとデータがおかしくなるんですね(笑)。そこで段々とグループ実験の時には手を動かさずに、「この実験によってこういう結果が出るといっているけれども、論理的にはまだ穴があるのではないか」などと理屈をこねて、評論をして回るようになりました。その頃から、どうも自分には実験科学者はあまり向いていないと思うようになりました。
当時の多くの教官には口じゃなくて手を動かすようにと言われていたのですが、その姿勢を面白がってくれていたのが当時の指導教官であった、動物行動学者の日高敏隆さんでした。その頃、日高さんに科学哲学の村上陽一郎さんのような人が好きだと話したら、「個人的に知っているから集中講義に呼んであげよう」ということで、当時東京大学に在籍されていた村上陽一郎さんを理学部の集中講義に呼んでくださいました。その当時、村上さんは出版されたばかりの『近代科学と聖俗革命』について、理学部の学生の前でかなり細かく講義してくれました。その後、村上さんに「先生の研究のような分野に進みたいのですが、大学院を受験してもいいですか」とお聞きしたところ、「受けるのは自由だけれど職はないよ」と言われて、何もわかっていないままに「はい、分かってます」と返事をしたのを覚えています(笑)。ちなみにその頃、村上先生が所属されていた科学史・科学基礎論専攻は東京大学の理学系研究科にあったこともあり、入学試験の一次試験は理学の分野でしたが、二次試験はいきなり哲学の分野が出るなどとんでもない構造でした。
沼田:科学哲学の道に進む上で、京都大学文学部の哲学専攻などは考えなかったのでしょうか?
小林:科学の哲学というと京都大学でも田邊元などが有名ですが、ご本人は大正時代の科学を対象としていました。私としてはむしろ現代の科学についての哲学的な理論に関心があったのですが、そういう研究をしている人は当時の京都大学文学部にはいませんでした。当時、現れてきた科学論や科学哲学をやりたいと思ったら東京大学しかなかったわけです。とは言え、同大学の源流機関は蕃書調所(洋書調所)というところなんですが、そこでは洋学者の養成システムが色濃く残っていたこともあり、当時の講座では英米の最新の哲学の議論を輸入し、それを解読して……といったことをやっている方々が主流でした。そこは、私が真にやりたいこととは少し違っていたものの何とか修士論文を書き、その後の博士後期課程では仲間うちで科学技術社会論(Science, technology and society:以下STS)に関する研究会なども行いました。
大学院を終えた後、村上先生のおっしゃったとおり職はすぐには見つからず、大学の非常勤講師と予備校教師で食いつなぎ、ようやく就職できたのが福岡教育大学でした。その後、南山大学に異動しました。当時南山大では3年勤めると外国に1年半行かせてくれる制度があり、その機会にロンドンに行きました。東京大学では英語の文献を読むトレーニングを受けていたので、イギリスの哲学者の名前もよく知っていました。ロンドンでは、院生の頃から読み慣れていた論文の著者がセミナーをやっていたので参加したりしていたのですが、受け入れ先の教授から、「日本から来たのだから君も何かしゃべれ」と言われ、その時に非常に困りました。というのも、これまで西洋人の書いた科学哲学の論文をたくさん読んできたので、自分なりの議論を組み立てようとしても西洋の科学の事例を使う羽目になってしまうのです。当時科学技術大国だった日本から来ておきながら自国の事例で語る内容がないことに気づき、結構なショックを受けました。その時に私は何をしてきたのだろうか、これから何をすべきだろうか、とちょっと真剣に考えました。

イギリスでの経験とコンセンサス会議
広井:イギリスでのご経験からどのようにして現在の活動に繋がったのでしょうか。
小林:イギリス滞在中のもう一つ印象的な出来事として、イギリスを含むヨーロッパでは当時、市民参加型のテクノロジーアセスメントとして、コンセンサス会議というものが注目されていました。当時のテーマの多くは遺伝子組み換え技術についてだったのですが、一般市民を20人ぐらい集めて研究者と一緒に議論させるといった枠組みで行われていました。いよいよ会議が始まるという時に、その準備をしているメンバーが、「今日は集めた一般市民のインタビューをするのだ」と言ったことがありました。何のためにインタビューするのかを尋ねると、「マッドかどうか確かめる」という答えが返ってきたんですね。この衝撃は今でも忘れられません。イギリスは階級社会の歴史を持っています。つまり、エリート層である研究者たちには一般市民に対する根深い不信感があり、集めてみたものの議論も成り立たないような無茶苦茶なことになるのではないかと恐れていたんですね。
私自身も、最初はこのような専門性を伴うテーマについて、ただの素人を集めて何を議論するのだろうという疑問を持つ程度の認識しかなかったのですが、この会議を準備している人たちといろいろ議論しているうちにだんだんとその意義が理解できるようになりました。当時はその様子を書くだけで論文一本になったと思いますが、そんな紹介だけでは満足できなくなっていたので、実際に自分も日本でコンセンサス会議をやってみよう、と思い立ち、1998年に大阪で実際にコンセンサス会議を実行しました。
大学院で行った高等教養教育
沼田:少し趣向を変えまして、大阪大学でのご活動もお聞きできればと思います。
小林:大阪大学での活動の一つの軸として、大学院での教養教育というコンセプトを立ち上げようとしていました。当時、これは旧帝大のどこもそうだろうとは思いますが、総合大学と言いながらも研究科が縦割りになっているので、単科大学の連合体以上のものではないのではないかという問題がありました。また大阪大学は他の旧帝大と比べてもアイデンティティの確立に苦労していたということもあり、当時の総長は「社会から信頼される専門家を作る大学」というコンセプトを立ち上げました。このためには市民社会の人たちとコミュニケーションできるような専門家をきちんと作らないといけないので、全学的な大学院のコミュニケーションデザインを考えるためのセンターとして、2005年に大阪大学コミュニケーションデザイン・センター(CSCD)というものを設立しました。
CSCDでは、分野を超えた学生が一つの部屋で議論をすることによって、自分の持っている思考の癖を自覚化させるような教育プログラムを作る実験を行いました。教養とは何かというのは難しい問題ですが、私が一番違和感を抱えていたのは、入学した際に最初に教養教育があって、その後専門に進んでいくというパスが自明視されていたことでした。この順序は絶対的ではないのではないか、と感じていました。私自身、京都大学の教養部で政治学の科目を履修したことを覚えています。義務的に選択した科目であり、内発的な履修の意欲はほとんどありませんでした。後年、ある程度専門を学んでいくと、当時の専門とは異なるのですが、あらためて政治学への関心が湧き起こるということがありました。この経験を踏まえ、もちろん専門的な教育は重要なのですが、教養教育が階層的に進むのではなく、同時並行的に選択できるような体制が良いのでは、という議論を行いました。これに加えて、大学院でも教養教育に関する科目をきちんと提供すること、また研究科を超えた繋がりが持てるような科目を作ることで、長期的にみてプラスになるのでは、といった議論を行いました。
この中ですごく印象的だったのは、放射性廃棄物の処分問題をテーマに学生に話し合ってもらった時のことです。テストランとして工学部の大学院生を10人集めてやると2時間弱で見解が収束したのに対し、複数の研究科から集まってもらった大学院生10人でやると、議論を始めて1週間経っても見解が収束しませんでした。社会に出てみると実際分野の違う人が集まっているわけで、そのような経験や教育についてももう少し重要視されるべきだと思いますが、今の日本では同じ思考傾向の集団で効率性に着目した教育ばかりが行われており、あまり良くない点だと感じています。
科学技術社会論学会(STS学会)の設立
沼田:小林先生はその後、科学技術社会論学会(STS学会)(*1)という学会を始められたと伺っています。そのような学問はそれまで日本になかったと考えてよいですか。
小林:結論から言うとイエスです。STSのルーツの一つとなっているのは、1970年代のアメリカで始まったSociety for Social Studies of Scienceという学会です。これを作った人々の中にはトーマス・クーンのパラダイム論(*2)に刺激を受けて、科学技術批判を行った人々がいました。その点で、この分野はジャーナリスティックでアクティビスティックなスタイルの研究が多い分野であったことは確かなのですが、それを少しアカデミックにするという動きが出てくるのは1990年代ごろではないかと思います。その当時、私たちは日本でSTS Network Japanという緩やかな連絡組織を作り、主に読書会をやっていました。STSに関する職のあては全くなかったこともあり、マニフェストのようなつもりで「科学見直し叢書」という本を4冊出しました。今から振り返るとこの本の内容の多くは科学社会学のニューウェーブの紹介に留まっていましたが、その中で「STSが社会に必要だ」といったことを書いたのは科学技術史学者の中島秀人です。
実はイギリスではSTSは教育プログラムとして始まっており、中等教育の教科書の副読本として使われていました。それまでイギリスでは、科学者は科学知識の正しいコンテンツのみを語り、科学という活動がどのような社会的な文脈の中で埋め込まれて機能し始めるか、あるいは社会にどんな影響を与えるかということに焦点を当てたような研究は、科学史研究を除くとあまりありませんでした。というのも、人文社会科学系の研究者は科学に対して遠く離れた立場からの批判はするものの、もう少しミクロな視点、つまり社会の中で具体的にどのように機能しているかに関する議論はあまりしなかったからです。STSはそういうところから生まれてきたんですね。
例えば、遺伝子組み換え農作物がなぜ生まれたか、という問いに対して、生物系の先生は遺伝子組み換えのための酵素が発見されて……というような議論をするわけですが、STSに近い発想でいくと、遺伝子組み換えの作物に対して知財が認められるようになり、遺伝子組み換え技術開発に膨大な研究費が投入されるようになったから、といった説明をします。これまでの理科の教科書というのは前者のメカニズム的な視点ばかりだったわけです。
一方イギリスでは、科学者にならない人、つまり市民社会に出ていく人に与えるべき知識はコンテンツの部分だけでいいのか、そうではなくて科学が社会の中で果たしている役割や正と負の効果などの社会的文脈をきちんと教えるべきではないか、という問題意識が生まれてきました。そういった視点から、イギリス人が作った教科書を読むと、自分たちが学んできた理科の教科書と全然違う世界が見えるわけです。これは私にとってすごく新鮮でした。日本の場合は、科学史の研究者に加え、科学教育、科学社会学の一部の人、理工系の研究者などがそのような分野に関心を持って集まって動き出したという経緯があるかと思います。
――――――
脚注
*1 詳しくは以下のWebページを参照。
https://jssts.jp/ (アクセス日:2024年3月4日)
*2 アメリカの科学史研究者トーマス・クーンが主著『科学革命の構造』(1962)で提唱した科学史、科学哲学上の理論体系。パラダイムを「一般に認められた科学的業績で、一時期の間、専門家に対して問い方や答え方のモデルを与えるもの」と定義し、科学の歴史をパラダイムの断続的な転換として捉え直す見方を提示した。
