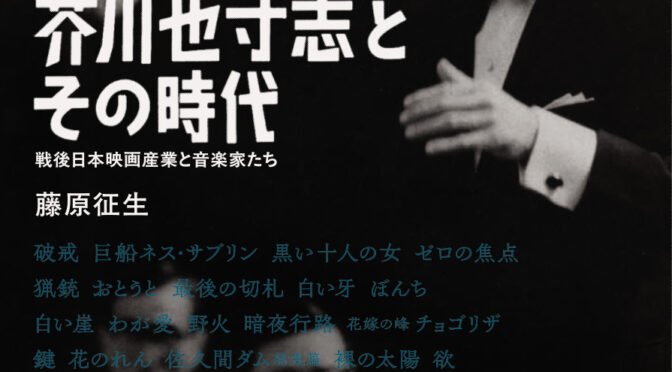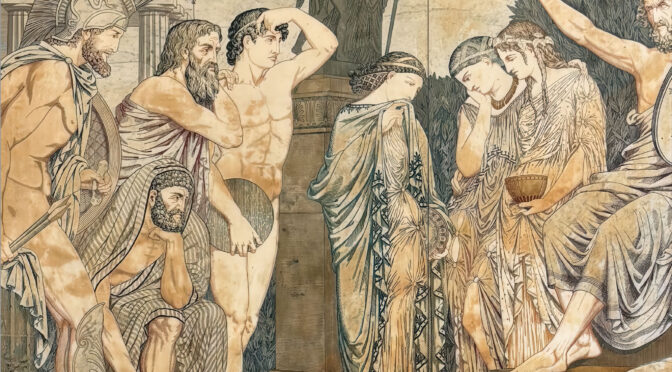温 秋穎『近現代日本における中国語受容史──メディア・教育・言語観』
2025.08.15
著者:温 秋穎(京都大学人文科学研究所 特定助教)
出版社:岩波書店
発行年月日:2025年3月27日
表紙.jpg)
書籍紹介
中国文学者の吉川幸次郎は日中戦争の最中に、「支那語の不幸」という文章を発表したことがある。そこで挙げられた不幸とは、「支那語」と国語が「同文」であるという万能思想、「支那語」は優しい外国語だという思想、③わが国古来の「漢文訓読法」という三点であった。彼はさらに、「支那語の不幸はすくはねばならぬ。学術のためにも、政治のためにも」と説いた。
現在に「中国語」と呼ばれることばがかつての「支那語」であるが、そのことばになぜ不幸がなぜ生じたのか?また、その不幸な「支那語」は、教養としての外国語である英独仏語と異なり、しばしば学術や政治の裏道に追いやられがちであったが、一度たりとも「教養語」にならなかったのだろうか?本書はこうした問題意識に基づいて、近現代日本における中国語の受容史と、中国語受容の言語観を記述するものである。
中国語は日本人にとって外国語のはずであるが、近代における入り組んだ日中関係ゆえに、そして漢字を使って表記される性格ゆえに、その言語の「他者性」は常に曖昧かつ複雑なものであった。このような、中国語に現れた文字と言語が絡み合った複雑な他者性は、とくに音声メディアと関係しているため、本書では中国語教材のメディアを切り口とした。具体的に、ラジオや出版物といったメディアを介した日本国内の中国語学習の場において、中国語を教養のある外国語として追求した教育者と学習者の言説と行動を考察し、これらの言動と思考の連鎖が当時の日本の中国認識、日中交渉にもたらした意味を検討した。
時期設定の起点となる1930年代は、新しい音声メディアが出現し流行し始めた頃で、ラジオ放送の「支那語講座」で正則な中国語が教えられたことは、〈声〉の中国語受容の大きな転換点であった。時期設定の終わりは、テレビという映像メディアのなかで同時代の中国の様子が具現化され、中国の「虚像」が「実像」に変わっていく1960年代後半としている。
メディアと大衆社会の時間軸のほかに、戦争と平和の時間軸も本書のなかに内包されている。1930年代の満洲事変や日中全面戦争は、日本国内の中国語ブームをもたらした。しかし、日本国内の中国語ブームはこれらの戦場の不在を前提としたものであり、中国語は敵国のことばどころか、親善友好のためのことばとされることが多かった。戦時下に流行った中国語は「日支親善」のための必須な知識であり、変種の教養であった。日本における第二次大戦の終結は1945年とされることが一般的であるが、日中関係の場合は「二つの中国」の問題によって大きく翻弄されていった。冷戦という危機の時代において、語学を通して一定の文化交流のルートが保たれた一方、遠い国への新しい想像、ないし新しい虚像も喚起された。
戦前と戦後の中国語受容史を記述することで、国家単位としての日本と中国の友好関係を称揚しようとしたわけではない。国家という属性をことばの再優先事項として考えることによって生じたさまざまな分断について、本書の第六章と終章で考察した。中国語教育者の工藤篁が国交正常化の前に、「親善とは常に欧米の先進国に対しての微笑である。英独仏は親善語学である。日中友好協会、そして友好商社員が、広州交易会のために友好語学を学習する。中国語は友好語学である。親善にはおだやかな微笑がある。軍艦の砲口をうしろにして、常に優雅であり、文化的である。実に紳士的である」と述べた通り、利益のための友好語学は時として暴力の脅しを背後に隠している。また、国家のためのことばは、常に個体に対する抑圧から免れえない。
本書では日中国交正常化の前後を受容史の一つの区切りとしたが、それから現在に至るまで、中国語を含めた諸外国語の教育と学習、受容の仕方はまた大きく変貌した。中国語を「教養語」とする目標はいま現在、すでに達成されたのだろうか。それは日本の中国理解、中国の日本理解に資するものになっているのだろうか。このような問いを、終章「もう一つの教養語という未完の課題」において読者に投げかけた。
しかしながら、受容された「結果」の一部についての良し悪しの価値判断は別として、他者理解を志向することばの倫理そのものが、他者の存在を介在するものでありながら、最終的には自己の物語を形成するものであると考えている。その倫理は他者へ開示されるものであるのと同時に、常に自己に回帰してくるものである。この意味で本書を、中国語という他者のことばを通して生成した日本人自身の物語として読んでいただきたい。