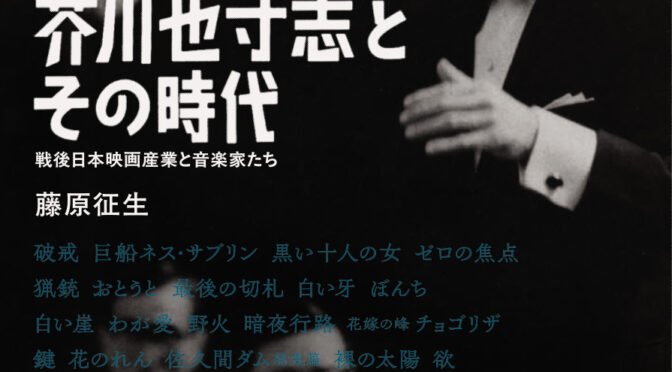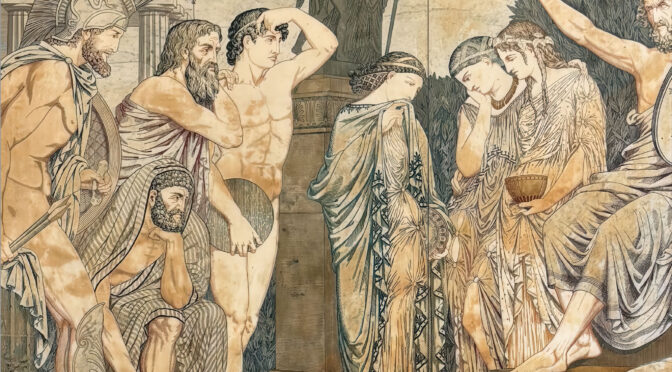石田 智敬『学習評価論における質的判断アプローチの展開:ロイス・サドラー学識の解剖と再構成』
2025.08.15
著者:石田 智敬(神戸大学大学院人間発達環境学研究科 特命助教)
出版社:京都大学学術出版会
発行年月日:2025年3月31日
表紙.jpg)
書籍紹介
たとえば、プレゼンテーション、小論文、各種のレポートといった成果物、すなわち正誤で単純に評価することができない課題、そして、何が良くて何が悪いのかがはっきり明確に定まっていない課題は、どのように評価すべきなのだろうか。近年、社会の構造変容を背景として、単純な知識・技能を評価する客観テストではなく、知識・技能を総合的・統合的に活用することを求めるような複雑な課題が、重視されるようになっている。このように、客観テストをはじめとする筆記試験以外の評価方法を導入し、学習成果を幅広く見取ろうとする動向は、理論、実践、政策の各次で力強く推進されている。
かくして我々は、単純に正誤で評価できない複雑なパフォーマンスを、どうすれば妥当に評価できるのかという問いに直面している。客観テストの答案とは異なって、複雑なパフォーマンスを評価することは明らかに容易ではない。本書で焦点を合わせる碩学、ロイス・サドラー(1943-)は、このような複雑なパフォーマンスを評価する方法について、思索を続けてきた教育評価の研究者である。
急いでことわっておけば、教育における評価は単なるねぶみに留まるものではない。教育における評価と聞いて、真っ先に連想されるのは、テストや通知表といった成績評価に関わる類のものであろう。ただし学習評価は、単に成績評価一一学習成果の到達点を認証し証明するものーに限定されるものではない。我々は、評価を通じて何ができていて何ができていないのかを把握することができる。そのため、評価は教育と学習活動をより良くするために欠かせないものである。改善のために行う評価のことを形成的アセスメントという。形成的アセスメントは、評価活動を学習者のねぶみの場としてではなく、成長に向けた学びの場として捉える。評価活動を通して、教師と学習者が一致協力して学習の改善に取り組むという、形成的アセスメントの考え方を理論化したのがサドラーである。「優れた評価は優れた教育の付属物ではなく、それ自体が優れた教育なのである」。サドラーはこのように述べて、学習評価を学びの中心に位置づける発想を打ち出した。
このように、比較的単純な知識・技能の習得を超えて、知識・技能を総合的・統合的に活用するコンピテンスの育成を企図し、それを促進し実現するための学習評価論の構築に挑んだのが、サドラーである。
教育評価研究においてサドラーは、1980年代に「スタンダード準拠評価」や「形成的アセスメント」といった考え方を理論化し、ルーブリックの使用やフィードバックの提供を推奨する現代の学習評価論を基礎づけた研究者であると理解されている。これらルーブリックやフィードバックといったアイディアは、現代の学習評価論を語る上で、どれも欠かせないキーワードとなっている。ところがしかし、サドラーはのちに、これらの考え方に対して根本的かつ徹底的な批判を展開するようになる。なぜサドラーは主張を転回したのか。自己批判にも映る、このようなパラドキシカルな立場は何を意味するのか。
本書は、これまで看過されてきた、現代の学習評価論の提唱者であり批判者でもあるというパラドキシカルな立場性を念頭に、ロイス・サドラーの所論を氏の研究史に即して読み解き、質的判断アプローチの学習評価論のさらなる展望を描き出そうとするものである。換言すれば、サドラーの学識の解剖を試みる本書は、氏の学識の再構成に挑戦することで、学習評価論の新たな可能性を切り拓く。
昨今の日本では、ルーブリックを活用したり、フィードバックを推進したりする学習評価の考え方は、政策レベルから実践レベルまで急速に広がりつつある。これらの考え方は無批判に称揚されることがしばしばで、クリティカルな検討はほとんど行われていない。本書では、このような学習評価の「当たり前」を問い直してみたい。「当たり前」にはどのような陥が潜んでいるのか。次代の学習評価はどう構想できるのか。
本書は、現代の学習評価論の理論的支柱であるサドラーの提唱と批判という刺激的な展開を読み解くことで、学習評価の新章を一考する。