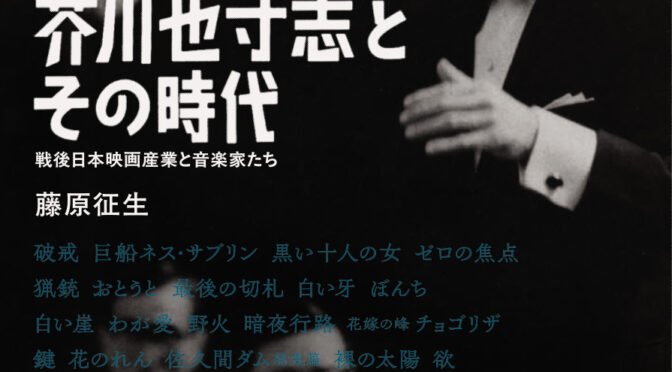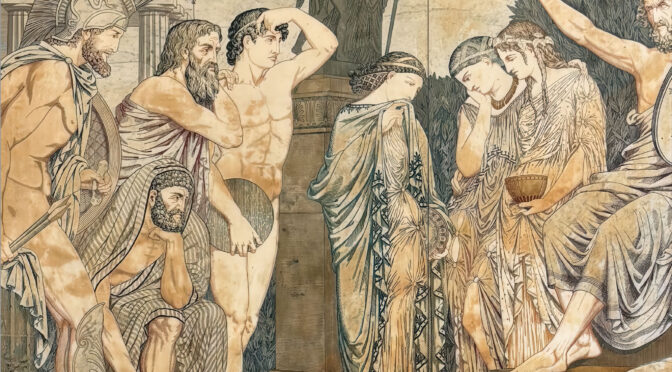澤西 祐典『芥川龍之介における海外文学受容 旧蔵書越しに見える風景』
2025.08.11
著者:澤西 祐典(龍谷大学国際学部 准教授)
出版社:ひつじ書房
発行年月日:2025年3月20日

書籍紹介
芥川龍之介の旧蔵書・洋書884冊を糸口とし、芥川龍之介における海外文学受容について論じている。三好行雄は日本近代文学館に芥川の旧蔵書が寄贈された際、「詳細に調査すれば、芥川龍之介論の有力な論点がいくつも引出せそうな、予感に満ちた旧蔵書の充棟は壮観である」と述べた(『日本近代文学館図書・資料委員会ニュース』第12号、1970年7月)。本書はまさに、この「予感に満ちた旧蔵書」に秘められた研究の可能性について実証的なアプローチから、可能な限りさまざまな角度から研究を押し進めた。
第1章においては、近代作家の旧蔵書研究の可能性について、これまでの研究で明るみになった点を例示しながら、総括的に研究の可能性について整理を行い、次章以降、個別の観点から、各章ごとに論点を変えて、芥川龍之介の海外文学との接点についてさぐった。まず第2章では、芥川が卒業論文で取り組んだウィリアム・モリス論について取り上げた。卒論の原本並びに草稿は現在所在がわからなくなっているが、周囲の証言と旧蔵書に残された書き込みを手掛かりに、芥川が象徴的な色彩美に富んだ詩人としてのウィリアム・モリスに惹かれていたこと、芥川の卒論がJ. W. Mackail. The Life of William Morris Vol.I (London, Longmans, 1912)の要約に近いものであった可能性などを指摘した。第3章においては、バーナード・ショーを取り上げ、芥川の受容実態を探った。芥川は戯曲家としてショーが一世を風靡した大正初期ではなく、むしろショーの人気が下火になった大正後期から昭和初期にかけて、熱心にショーの著作を読み込んでいた様子について詳述した。その一つの結実として、正続「西方の人」(『改造』1927・8、9) におけるAndrocles and the Lionの序文の影響を論じた。
第4章では、芥川の代表作「地獄変」について、原作ともいえる作品、ピエール・ルイス「芸術家の勝利」の存在を指摘した。芥川は同作を1918年1月中旬に読了し、「地獄変」を同年5 月から連載している。両作には(1)逸話・武勇伝の列記、(2)語り手による回想形式、(3)芸術家と対立する時の為政者の登場、(4)名画の縁起物語、(5)芸術至上主義を徹底した芸術家(もしくは芸術作品)とその勝利、(6)鎖で縛られたモデルといった要素が共通してみられる。また、画家が描き出す画題が、神々から火を盗んだギリシア神話の英雄<プロメテウス> から炎熱地獄を描く<地獄変>と変わった点は、<英雄伝>から<芸術作品>の神話へのテーマの変奏、<芸術作品>に関わる人間たちに待ち受ける<地獄>の描出という主題の変遷を象徴していることも指摘した。原作と呼んでも差し支えないような典拠の浮上は、芥川にとって創作と は何か?という問いを浮上させるとともに、芥川の芸術家としての自負のよりどころを明かしている。そのほか、ピエール・ルイスが永井荷風や谷崎潤一郎にとっても重要な作家であったことを本章では指摘した。
続く第5章では、特定の本を参照するという形ではなく、旧蔵書全体を眺めるという主旨のもと行った調査から得た成果をまとめている。その一つとして、蔵書の頁の間から倉田百三『出家とその弟子』を求める書きかけの書簡が見つかり、新資料として提示した。また、旧蔵の辞典からは辞書を模したようなメモが見つかり、芥川の辞書愛好家としての側面に改めて光を当てた。そのほか、初恋相手に宛てたと思われる押し花の発見などについても記した。
第6章では、芥川が編纂したThe Modern Seiries of English Literature全八巻について論じている。これは旧制高等学校の学生向けに編まれた英語副読本であるが、芥川の怪異趣味が色濃く出た叢書でもある。加えて、芥川が「新しい英米の文芸」作品に拘っていたことを、その種本を明かすことで示している。(このアンソロジーについては未訳作品を中心に、柴田元幸氏との共編で『芥川龍之介選 英米怪異・幻想譚』(岩波書店)として刊行した。)
第7章においては、芥川が英語から翻訳した作品と旧蔵書にある英語原文の比較を手掛かりに、芥川の文章について考察した。芥川が翻訳において、三人称代名詞の使用を避けていることを受け、芥川が実作においても作品ごとに三人称代名詞の<常用>/<避用>を使い分けている事実を突き止めた。作品の特徴によって使い分けがなされており、<避用>はいわゆる王朝物と現代を舞台にした怪異小説に偏っていた。反対に、切支丹物や江戸期を舞台にした小説、怪異小説を除く現代小説では三人称代名詞は常用されている点などを指摘した。
第8章では、芥川にとって「翻訳される」という体験、あるいは「翻訳を読む」という体験が意味するところに探った。生前に「翻訳される」という体験を持っていた芥川は、<翻訳>という場に立ち現われる「蜃中楼」を愛する読者でもあった。同様な現象は、「世界文学」が注目される現代でも(当然ながら)起こり続けており、「世界文学」として読まれる際、翻訳先の言語圏で「あらかじめ奪われている体験」があることを具体的に指摘した。また、芥川旧蔵書に立ちかえり、芥川が見ていた旧蔵書越しの「世界文学」像を紹介した。第九章では、旧蔵書から離れ、 国外に散逸した資料に着目した。UCバークレー校に保管されている「母」直筆原稿を基に、芥川が触れた<海外>と彼の実作の関係性に触れた。
上記のように、日本近代文学館や山梨県立文学館、神奈川近代文学所蔵の旧蔵書にある洋書を主たる手掛かりに、これまでの先行研究の穴を補てんするような形で芥川龍之介の海外文学受容について論述している。また付録として、日本近代文学館・山梨県立文学館・神奈川近代文学館に保管されている芥川旧蔵書・洋書844冊への書き込みの悉皆調査一覧および読書年譜を附した。