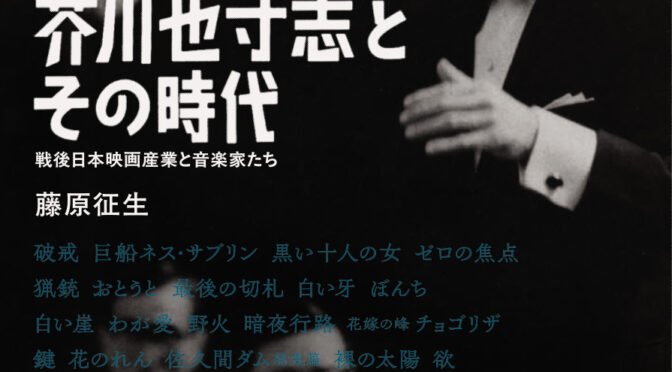榮福 真穂『スピノザの観念説』
2025.08.11
著者:榮福 真穂(日本学術振興会 海外特別研究員・フローニンゲン大学 客員研究員)
出版社:京都大学学術出版会
発行年月日:2025年3月31日

書籍紹介
本書を貫く問いは、17世紀オランダの哲学者スピノザが「観念」をどのように捉えていたかということである。スピノザの話をする前に、いくつか前置きをしておく必要があるだろう。まず、「観念」という言葉は一般的な日本語話者にとってあまり馴染みがないかもしれない。英語のideaに相当するので、「いいアイデアだね」などと言うときの「アイデア」のようなものだと理解してもよい。つまり、人間が心に抱く考えのことである。このような「観念」の使い方は、じつは17世紀に成立したものだと考えられている。17世紀には多くの哲学書がラテン語で書かれたが、ラテン語の「観念/イデア(idea)」は、17世紀以前には「人間が心に抱く考え」というような意味では使われていなかった。中世において、「イデア」は神が持つものであり、人間が持つものではなかったのだ。神が持つものなのだから、当然、それが間違っているなどということはありえない。他方で、人間が心に抱く考えとしての「観念」は、間違っていることもありえる。このように、「イデア」から「観念」へ、同じ一つの言葉がまったく異なる使われ方をするようになった、そのきっかけは17世紀にある。
この転換を決定的なものにしたのが、スピノザよりも少し前に活躍した哲学者、デカルトであった。デカルトは、人間が心に抱く考えを広く指し示すものとして「観念」という言葉を使う。デカルトの哲学が大流行したことで、「観念」の新しい用法も、少なくとも哲学者にとって一般的なものとなった。デカルト以降の17世紀の哲学者たちは、スピノザも含め、人間の心のはたらきを説明するのに不可欠なものとして、「観念」という言葉を重視していた。そして、それが重要であるからこそ、彼らはそれぞれに独自のニュアンスをまとわせて「観念」という言葉を使っていた。それゆえ彼らの哲学の独自性は、「観念」に込められた意味合いの独自性と深く結びついている。哲学史において、「観念」という言葉がこれほど中心的な役割を果たしていた時代は、17世紀のほかにはない。
このような状況の中で、スピノザは「観念」をどのような意味で捉え、そしてそれは彼の哲学体系とどのように結びついているのか。この問いは、デカルトの「観念」をどのように受容しているか、という問いと切り離すことができない。そこで、本書はまず第一部で、デカルトの「観念」の取り扱いについて論じている。ここで注目するのは、デカルトにとって「観念」は二つの側面を持っているということだ。一方では、観念には心の外にあるものを表象する、という特徴がある。他方で、観念はそれ自体で心的な存在者としての身分を与えられている。要するに、私が心に抱くさまざまな思考は、その内容はその都度異なるかもしれないが、どれも「私の思考」であることに変わりはない、ということを言っているのである。デカルトは、これら二つの側面を区別して使っていたが、結局どちらの側面を主要なものとみなせばよいのかという謎が残ってしまった。こうして、デカルトの影響のもとにあるマルブランシュ、アルノー、ロックらは、観念の二面性のどちらを重視するかという観点から立場が分かれることになった。
このような「ポスト・デカルト」の状況において、スピノザの観念の取り扱いを見てみると、スピノザはデカルトが区別した観念の二つの側面をほとんどそのまま受け入れていることに気づく。本書の第二部では、スピノザがデカルト的な観念の二つの側面を受け入れつつ、そこからどのように逸脱しているかを明らかにしている。逸脱のポイントは、両者の重点の違いにある。デカルトは、観念の二つの側面のうち「心の外にあるものを表象する」という面を重視していたのに対し、スピノザは観念が「心的な存在者である」という面を重視していた。スピノザの面白いところは、観念が心的な存在者であるということを、物体が物体的な存在者であるということとまったく同じ重さで捉えているところだ。本書ではこのことを、心的か物体的かにかかわらず「何かであるもの」を意味する「事物(res)」という言葉を使って、観念の「事物性」と呼んでいる。観念は、心の中にあるもののはずなのに、スピノザにとっては物体と同じように「事物」なのである。
「心の中にあるもののはずなのに」と私は言った。しかし、じつはこれは正確ではない。スピノザにとって、観念とは、「実体」という宇宙そのものであるような存在が、特定の仕方で個別に現れたものにすぎないからである。このように、宇宙そのものである「実体」の観点から、スピノザの叙述は始まる。そして徐々に「人間」へと焦点が絞られていく。第三部では、このような叙述の順序を踏まえ、「実体」から「人間」へと観念を論じる場が移っていく過程を取り扱っている。ここで初めて、観念が正しい/間違っているということが論じられるようになる。経験上、私たちの観念はその多くが間違っている。この間違った観念とどのように向き合えばよいか、本書ではスピノザなりの方法論を取り出してみることを試みた。
本書は、「観念」という17世紀の中心問題に真正面から取り組んだものである。主題の性質上、込み入った話も多いが、できるだけ明瞭な記述を心がけた。狭い意味での専門家のみならず、広く哲学に関心のある読者のかたに楽しんでいただければ幸いである。