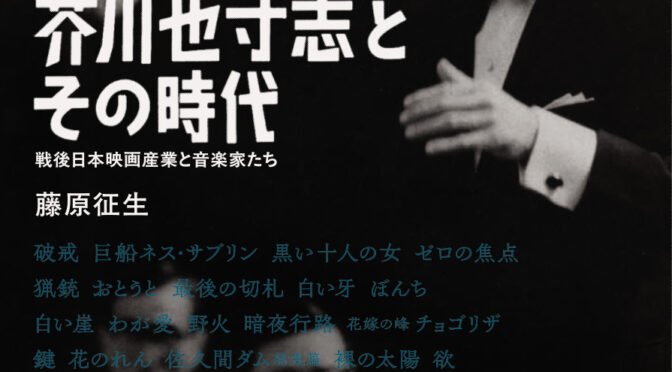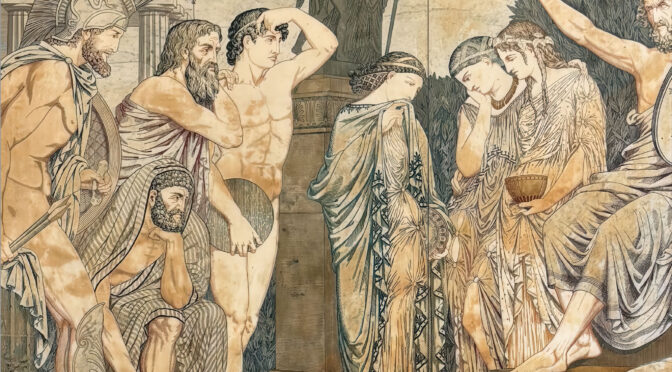村角 愛佳『なぜ「同意に基づく武力行使」が正当化されるのか: 理論と実行からの探求』
2025.08.11
著者:村角 愛佳(神戸大学大学院法学研究科 特命助教)
出版社:京都大学学術出版会
発行年月日:2025年2月

書籍紹介
近年、国家の同意に基づく武力行使、すなわち一国が他国に自国領域での武力行使を認めるケース(「同意に基づく武力行使」)が急増しています。とりわけ内戦下にある国家、あるいはテロリストにより一部領域を支配されている国家が、他国に軍事介入を要請する事例が目立ちます。そのほかにも、アフリカ連合(AU)や西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)といった地域的国際機関が、その加盟国の事前の同意に基づいて、軍事介入する可能性も出てきました。こうした同意に基づく武力行使は、国家の同意・要請を正当化根拠とするため、一見何の問題もないようにも見えます。日本に米軍が駐留していることに対しても、誰も国際法上違法とは思わないでしょう。なぜなら日米安保条約や地位協定といった条約が存在し、そこに日本の同意が反映されているからです。
しかし、なぜ同意によって武力行使が正当化されるのかという理論的問題は、十分に解明されてきませんでした。というのも、現代国際法では武力行使禁止が基本原則であり、しかもそれは強行規範(国家の同意によっても逸脱が許されない規範)と考えられているからです。武力行使の禁止が強行規範であることと、同意により武力行使が正当化されることは、どのように整合的に理解すればよいでしょうか。
理論的問題をひとまず置いておくとしても、いかなる場合に同意によって武力行使が正当化されるのかという実践面の議論があります。例えば上で挙げた例のうち、内戦に陥っている国家は、他国に軍事介入を要請できるのでしょうか。要請を出すのは政府ですが、内戦下の政府はその国家を代表している(したがって適切に要請を出す権限がある)といえるでしょうか。またもしその政府が、自国民に対して化学兵器を使用するような政府であれば、どうでしょうか。人権侵害の甚だしい政府の要請に基づいて、他国が軍事介入をすれば、それはその政府の地位を強めることになりかねません。
これまでこの問題を議論してきた先行研究は多数あります。しかし不可解なことに、理論的問題と実践的問題が関連して論じられてきませんでした。理論的問題について学説Aと学説Bの対立があり、実践的問題についても学説Cと学説Dの対立があるとして、学説Aを採用する論者は学説Cに立ち、学説Bを採用する論者は学説Dに立つというわけではないのです。理論(なぜ同意によって武力行使が正当化されるのか)と実践(いかなる場合に同意によって武力行使が正当化されるのか)は、本来関連するはずですが、全く別個に論じられてきました。それによって理論と実行の間に齟齬が生まれ、同意に基づく武力行使に関する議論は断片的かつ混乱したものとなっていたのです。
本書はこのような学説の現状を指摘し、その原因を探るところから始まります。理論的問題は、結局武力行使禁止原則の強行規範性を疑うことになるか、強行規範そのものの概念を問うことになる難問であり、敬遠され回避される傾向があります。一方で、近年の実行の増加に伴い実践的問題の解決は急務であり、それに取り組む先行研究は増加の一途を辿っています。しかし理論的問題をよそに場当たり的に実践的問題のみを扱っているため、本来は関連すべき両問題が別個に論じられているのです。
そこで本書は、理論的問題と実践的問題を解決し、かつ両者を整合的に理解するための、新たな理論的枠組を提示します。それは具体的には、武力行使禁止の伝統的な「国家対国家」的理解に加えて、人間の利益に焦点を当てた「人間的視座」を導入し、武力行使禁止原則そのものを再構築するものです。というのも、近年の先行研究も指摘するように、実行においては、これまでの「国家対国家」的理解では語られない、人間の利益に着目する価値が光を当てられるようになってきました。それは、これまでの国家中心的な枠組みでは、国際社会の現実を捉えきれないことを示しているように思われます。本書は、実践的問題のみならず理論的問題においても、この人間的視座を取り込み、さらに強行規範性を人間的利益に見出すことで、上述の難問を乗り越えられると主張しています。
したがって本書の意義は、武力行使禁止原則自体を捉え直す新しい理論的認識枠組を提唱し、同意に基づく武力行使をめぐる理論的・実践的問題を整合的に説明することのできるモデルを打ち出していることです。そしてそれを通して、国際法における武力行使・国家・人間の意味を探求しています。国際法は伝統的に、主権国家間の法として存在し、国内の人びとは、国際法の客体として受動的にしか捉えられないものでした。しかし第二次大戦以降、国家よりも人間を保護することを主眼とした国際法規範が誕生し発展してきました。国際人権法や国際人道法がそうです。「国際法の人間化」とも評されるように、国際法はその国家中心的な志向を和らげ、これまで一般に国際法の上では阻害されてきた人間に目を向けるようになったのです。この国際法全体の潮流の中で、未だ国家中心的な性格を色濃く示すのは、武力行使の分野であるといわれてきました。本書はこの武力行使の分野にも、人間的視座が核心的な役割を果たしていることを示しています。