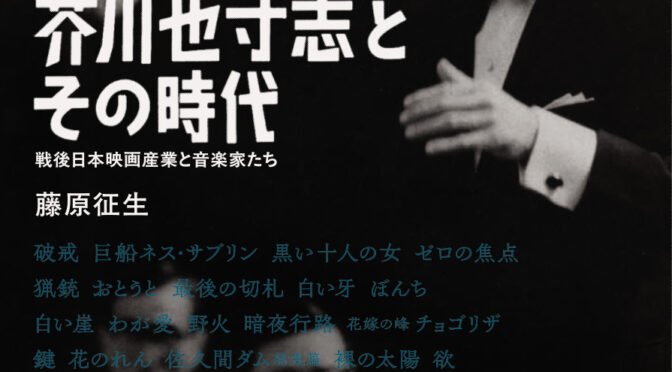斎藤 賢『「史記」はいかにして編まれたか-蘇秦・張儀・孟嘗君列伝の成立』
2025.08.10
著者:斎藤 賢(日本学術振興会特別研究員₋PD)
出版社:京都大学学術出版会
発行年月日:2025年3月20日

書籍紹介
本書は『史記』がいかにして編纂されたのか、という問題を、特に中国戦国時代関連の列伝を中心に検討することで明らかにしようとしたものである。
秦の始皇帝の天下統一によって幕を閉じる戦国時代には、社会・思想・制度・技術など様々な面で飛躍的な発展が生じたとされる。とりわけ、諸侯の並立する春秋時代に続き、その後二千年の長きにわたって中国史を規定することになる皇帝制を胚胎した戦国時代は、ある意味で終わりの時代であり、かつ始まりの時代でもあった。中国史上におけるその重要性は看過できない。
そして、その戦国時代を通時的に理解しようとする際にまず参照せねばならないのが、本書の主題となる『史記』なのである。『史記』は伝説的な五帝の時代から司馬遷の同時代である前漢中期までを通時的に記した歴史書であり、中国古代史を理解する上で欠かすことのできない史料である。しかしながら、戦国史研究にとり、その重要性は他の時代にまして大きいということができる。それはなぜか?それについては、主に現在の史料状況が関連する。
戦国時代の前後に位置する春秋時代や前漢時代の研究については、『史記』以外にもそれぞれ『春秋左氏伝』や『漢書』といった編年的史料が利用可能であり、『史記』のみに依存しなければならないというわけではない。それに対し、戦国時代を通時的・体系的に記した編年史料は現在のところ『史記』がほぼ唯一と言えるのである。このように考えれば、戦国史研究における『史記』の重要性が了解されるだろう。
ただし、実は戦国史研究の史料として『史記』を利用するには種々の課題が山積している。その例として、君主の在位年代や事件に関する紀年の錯誤や相互に矛盾する記述などを挙げることができるが、これらが『史記』を史料として利用する際の障碍になっていたのである。そして、このような問題を解決するためにはまず、『史記』の編纂時にどのような原資料が採用され、それらがいかに組み合わされたのか、といった編纂の過程と手法を明らかにする必要があると考える。このような作業を通じて『史記』の記述がいかなる過程を経て形成されたのか、という点を解明することが、戦国史のみならず史料としての『史記』の性格を把握するために不可欠の基礎なのである。
このような問題意識に基づき、本書では戦国中期の三列伝-蘇秦・孟嘗君・張儀列伝-を取り上げる。
この三人はいずれも戦国時代中期に活躍したとされる人々であり、『史記』にはその波瀾の生涯が豊かな筆致で描かれている。以下に彼らの生涯と事績をかいつまんで紹介しよう。
蘇秦は洛陽出身の人物とされ、鬼谷先生のもとで勉学した後、諸侯に遊説して立身を図るが、何度も失敗を重ねながらも終には合従策を実現させ、六国の相となる。しかし、その後、諸侯の足並みはそろわず合従が崩壊すると、燕国のために斉国を疲弊させることを目的として、斉で活動を続けていたが、最後には斉王に寵愛される蘇秦を妬んだ斉臣らによって暗殺されてしまう。
張儀は蘇秦とともに鬼谷先生のもとで勉学し、秦の国に仕えて秦相となる。その後、秦と魏や楚との間で活躍を続けていたが、蘇秦が死ぬと、連衡を成立させて合従を打ち破り、秦に有利な情勢を生み出した。しかし、秦王との関係がうまくいかず、秦を離れて魏に赴き、そこで生涯を終える。
孟嘗君は斉の人物であるが、秦の相となったこともある人物であり、食客三千人を抱える封君としても知られる。彼は当初斉のために楚や魏、秦と対抗していたが、後に斉王と不和となり、孟嘗君の死後は斉と魏によって封邑の薛が滅ぼされ、子孫も後を絶ったとされる。
しかし、これらの列伝に記された内容は互いに矛盾し、あるいは年代や時代背景の点で不可解な部分が認められる場合がある。その中でも特に蘇秦列伝の記述は矛盾が最も多く、従来議論が積み重ねられてきたが、なお見解の一致を見たとは言い難い。
本書でこの三人を取り上げた理由として、まずは彼らの戦国史における重要性が挙げられるであろう。特に六国を合従させて秦の東進を押しとどめたとする事績が史実であるならば、その戦国史の動向に与えた影響は極めて大きいものであったはずである。これらの点についても議論が重ねられているが、その基礎となる『史記』の原資料と編纂方法の追究が求められる。
また、他に技術上の理由を挙げることができる。戦国時代の史料について言えば、戦国前期が現状では最も少なく、中期~後期はそれに比して増加する傾向にある。一方、戦国紀年を復元する最重要史料である古本『竹書紀年』には戦国後期に関する記述が無く、年代を修正する術がない。つまり、戦国後期の記述については年代の錯誤を手掛りとすることが困難となるのである。また、『史記』に類似する説話が多数載録されている『戦国策』には、戦国中期のエピソードが多く残っており、これらを『史記』と比較することができるという利点がある。
これら諸点を考慮して、戦国中期を対象としたわけであるが、本書の分析方法と結果は『史記』の他の篇の分析にも有用であるだろう。また他の文献の分析に際しても、一つの指針となりうるのではないかと期待する。