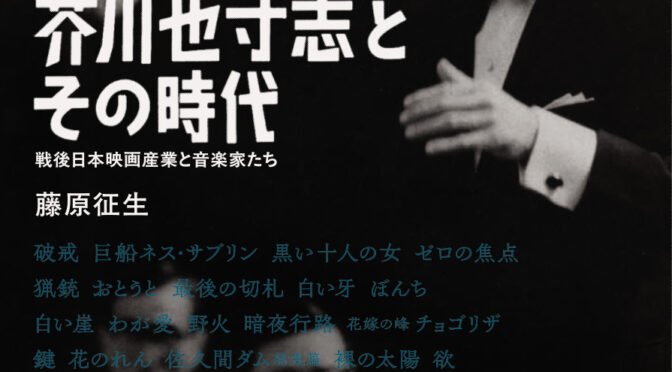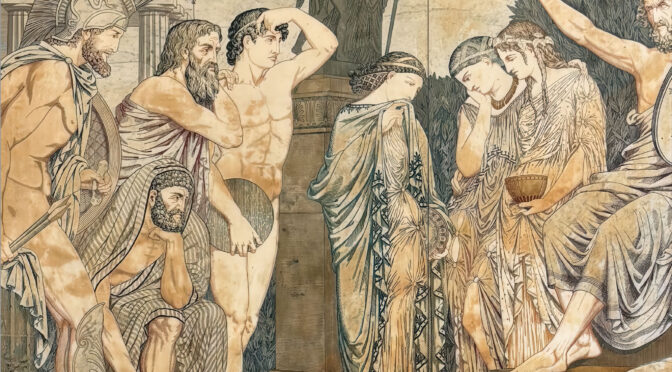久冨 峻介『ドイツ古典哲学と「学」の精神史:カントからヘーゲルへ』
2025.08.10
著者:久冨 峻介(京都大学非常勤 講師ほか)
出版社:京都大学学術出版会
発行年月日:2025年3月31日
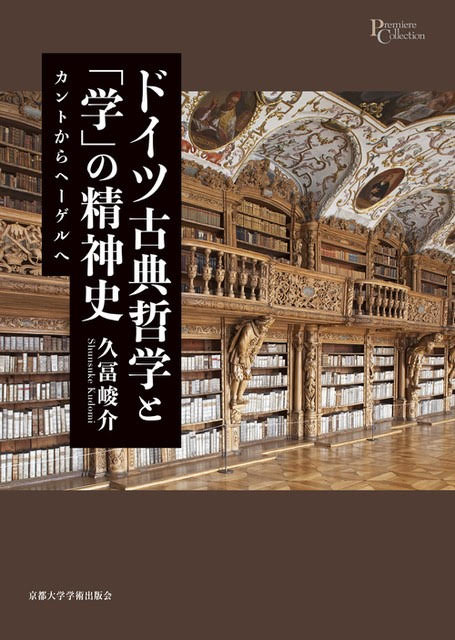
書籍紹介
今日の研究では「観念論はカントからフィヒテ、シェリングへと発展し、ヘーゲルにおいて頂点に達する」という枠組みは支持されていない。そうした教科書的な整理では、本来ポスト・カント時代の哲学的論争が持っていた重要な要素が捨象され、単純化されてしまうため、論争の争点もその多様で複雑な側面も見えなくなるからである。そのような従来の研究を反省し、古き「ドイツ観念論」観を払拭すべく、近年ではポスト・カント時代の哲学を「ドイツ古典哲学」と呼ぶことが好まれている。
本書は、ポスト・カント時代の哲学を単線的関係ではなく、複合的な対立を持つ「星座(Konstellation)」の布置関係として描くという「コンステラツィオン研究」の理念――この研究を世界的にリードしたのがD・ヘンリッヒ(1927‐2022)である――を引継ぎ、「一等星」「二等星」「三等星」どうしのあいだの対立を「学」の理念の進展に沿って描き出すことを目的にしている。それによって、これまで国内外で長きにわたってすでに多くの研究がなされてきたこの思想史に広がりと厚みを持たせることを目指した。そのために本書は1781年から1807年までの26年間のドイツの思想界をターゲットにし、『純粋理性批判』『全知識学の基礎』『精神現象学』はもとより、当時影響力を持っていた書評、著作論文の内容、さらには書簡も検討している。このことを通じて、「星座」間の位置関係をより詳細に、具体的に確定し、当時の論争の核心を従来よりも鮮明に浮かび上がらせている。
第一部では、フィヒテが「学」構想として『全知識学の基礎』を公表するまでのドイツの思想状況をスピノザ主義と批判哲学の二つを軸にして検討した。そこでスピノザ主義が18世紀のドイツでどのように受け止められてきたのか、ヤコービの『スピノザ書簡』のインパクトがどこにあったのか、『純粋理性批判』の理念がどのようにして普及したのかを論究し、その流れのうちにヤコービのカント批判とマイモンの「超越論的哲学」を位置づけた。とりわけ、マイモンがどのようにカントを吸収し、自らのスピノザ主義と両立させたのかはこれまでまったく明らかにされてこなかった。本書一部二章、二部五章では、カントからフィヒテへの進展を捉えるうえでマイモンがいかに重要だったかを究明している。
第二部では、ヘルダーリンとヘーゲルとシェリングの教師であったフラットが当時の論争でどのように立ち回り、「ドイツ古典哲学」の発展にどのように寄与したのかを解明している(三章)。フラットは国内の研究ではほとんど名前しか知られていないような状況であり、国際的にも部分的に論じられているだけにすぎない。彼が当時どのようにカントを批判し、フィヒテを主導し、ヘルダーリンらの学生に影響を与えたのかはほぼ明らかにされていなかった。本書第二部三、五章は長年空白のままにされてきたこの空白を埋めようとした。その他に、本書はフィヒテによるシュルツェとの対決(五章)、およびシェリング、ヘルダーリン、ヘーゲルとフィヒテ哲学との対決を究明し、18世紀末のドイツで「知識学」という新たな思想的潮流に若き彼らがどのように反応し、それに触発され、フィヒテを乗り越えようとしたのかを明らかにしている(六、七章)。本書では、ほとんど宗教研究にのみ従事していた若きヘーゲルが哲学的な知識を涵養するためには、ヘルダーリン、シンクレーア、ツヴィリンクとの「精神の連盟」での討論が不可欠であったこと、および同サークルではかなり先進的な哲学的議論が交わされていたことを実証している。
第三部では、「学」の樹立を本命の課題としてきた「ドイツ古典哲学」の進展の最終局面にヘーゲルの『精神現象学』を位置づけるべく、同書の「学」構想を論じている。これは、従来の研究でいわゆる「『精神現象学』の建築術」「現象学の論理学」問題として知られてきた課題である。著者は、この研究史上の問題の持つ思想的的な意義はこれまで正当に評価されてこなかったと考えている。たとえば、「建築術的読解」はヘーゲルの豊かな思想内容を論理的なカテゴリーに還元する形式主義だとか、あるいは「学」構想はヘーゲルだけの独自の発想法だとかいった誤解をしている研究者がいまなお多く存在しているのである。「ドイツ古典哲学」のなかに『精神現象学』を位置づけ直すことで本書が証明しようとしているのは、ヘーゲルの本来の狙いや同書の思想史的な意味、コンテクスト上の意義に他ならない。本書の提示した解釈によれば、『精神現象学』には独自の「体系の技術」(つまり、「建築術」)があり、その方法論こそが「現象学の論理(学)」と呼ばれてきたものの正体である。こうしたヘーゲルの発想は、彼を「ドイツ古典哲学」の展相の最終局面に位置づけることによって初めて見えてくる。「学」の「建築術」の問題と、『精神現象学』の「建築術」という二つの難題について同時に答えようとしたのが第三部での著者の試みである。
本書は、世界的には常識となりつつある思想史を複合的な関係(コンステラツィオン的な関係)と見なす研究の潮流を日本でも盛んにするべく、「ドイツ古典哲学」研究を標榜している。本書をきっかけにして、個別の思想家研究だけではなく、思想史の研究として同分野の議論がより深まり、活発になることを願って公表されるものである。