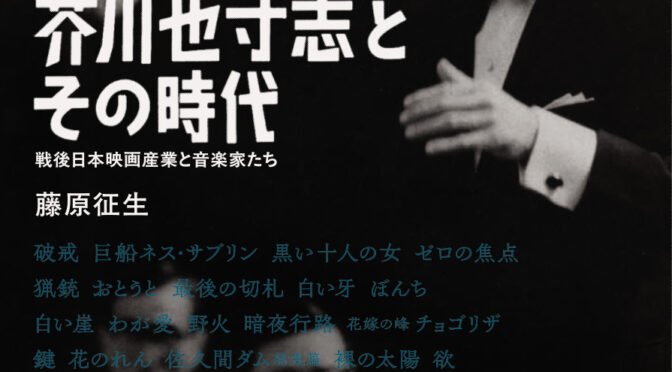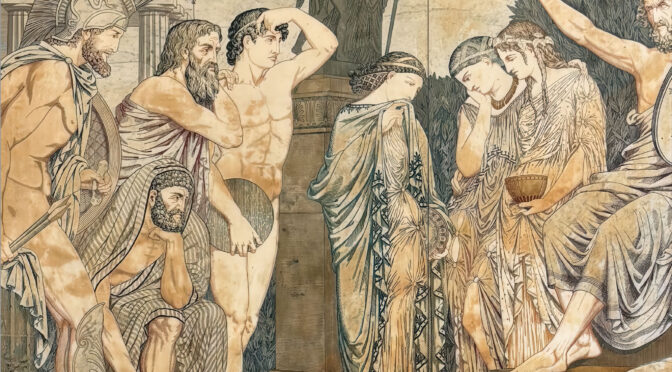髙坂 博史『新冷戦をこえて―ヨーロッパデタントから冷戦の終焉へ―』
2025.08.10
著者:髙坂 博史(名古屋市立大学大学院人間文化研究科 講師)
出版社:名古屋大学出版会
発行年月日:2025年3月31日
表紙-scaled.jpg)
書籍紹介
昨今、「新冷戦」という言葉を目にする機会が増えている。それは、米中間の対立やロシアによるウクライナ侵攻をはじめとする、国際情勢の悪化と冷戦時代への回帰を映し出している。しかし、時代をさかのぼれば、「新冷戦」はもともと別の文脈で使われていた言葉であった。「新冷戦」とは、1970年代末から1980年代半ばにかけての米ソ超大国間の対立が激化した時代を指す言葉だったのである。当時、世界の核兵器の数は過去最多となり(その記録は現在に至るまで塗り替えられていない)、世間では戦争に対する恐怖感が広く認識されていた。アメリカでは米ソ間の全面核戦争を描いた映画である「ザ・デイ・アフター」がヒット作となり、西ヨーロッパでは反核デモが街角を埋め尽くしている状況であった。そして、偶発的な戦争勃発の危機は決して絵空事ではなかった。1983年9月のソ連軍による大韓航空007便の撃墜事件は、偶発的な事案が悲劇へとつながることを知らしめるものであった。ジョージ・オーウェルが『1984年』で描いたディストピア世界が、小説とは異なる形で現実になったかのようであった。
このようななか、外交を通じて国際緊張の緩和を目指す勢力がいた。それが、フランス、イギリス、西ドイツをはじめとする西ヨーロッパの国々である。これらの国々は、1970年代にヨーロッパで全盛期を迎えたデタント(国際政治の緊張緩和)を持続させ、東西関係の安定化を目指していた。そして、その取り組みの中心に位置づけられたのが、「大西洋からウラル」におよぶヨーロッパ全域を対象とした、信頼醸成措置の導入と通常戦力の削減を目指す「ヨーロッパ軍縮会議」(Conference on Disarmament in Europe)であった。当時、ヨーロッパは東西対立の最前線の一つであり、バルト海からアドリア海へとおよぶ「鉄のカーテン」をはさんでNATOとワルシャワ条約機構の膨大な戦力が集中していた。世界のホットスポットの一つだったのである。ヨーロッパ軍縮会議は、この問題に対処して偶発戦争や奇襲戦争を防止することに加えて、東西間の安全保障対話のチャンネルとなることを目指すものであった。
本書では、西ヨーロッパの国々がヨーロッパ軍縮会議を発案し、外交交渉を通じて米ソ両超大国を巻き込んでいく過程を明らかにしている。とはいっても、この会議はすぐに開催されて成果を上げたわけではない。会議構想の出現から会議の具現化には実に6年以上という長い時間(1977年から1984年)を要し、また会議が開催されてから妥結に至るまで3年間(1984年から1986年)かかることになった。最終的には、ヨーロッパ軍縮会議は1986年に妥結し、冷戦末期に結ばれた数々の軍備管理・軍縮合意に先鞭をつけた。軍事的な対立を和らげ、冷戦終結の下準備をしたのである。そこで、本書はこの10年間を取り上げて、ヨーロッパ軍縮会議での対話が国際政治上で大きな意味を持ち、「新冷戦」のピークの克服に貢献したこと、さらには同プロセスでは西ヨーロッパの国々が大きな役割を果たしたことを実証した。
本書の特徴は、イギリス、フランスおよびアメリカの公文書館が所蔵する一次史料を活用したマルチ・アーカイバルなアプローチを取っていることである。複数国の史料を活用することで、多数の主体が関与する複雑な外交交渉の実態を浮き彫りにすることを試みた。そして、従来の研究では米ソ両超大国の役割に注目が向けられがちであるなか、水面下では西ヨーロッパの国々が主要な役割を果たしたことを描出した。
本書が扱うのはあくまで歴史上の事象であり、本書も第一義的には国際関係史に貢献することを目的としている。1980年代の一次史料が順次公開されるなか、それらを活用して冷戦の「終わりの始まり」をめぐる新たな知見を提供することが最大の目標である。しかし同時に、本書は今後の国際政治を考える手がかりも提供している。まず、ヨーロッパの安全保障問題を扱う本書は、戦火に揺れるヨーロッパの国際秩序の過去と未来を考えるヒントとなるであろう。さらに、アジアの安全保障環境が厳しさを増すなか、米中の狭間に立たされている日本が今後取るべき道についても示唆を与えるものとなろう。
以上、本書の概要を簡潔に紹介した。ご関心をお持ちの方には、ぜひ本書を手に取っていただければ幸いである。