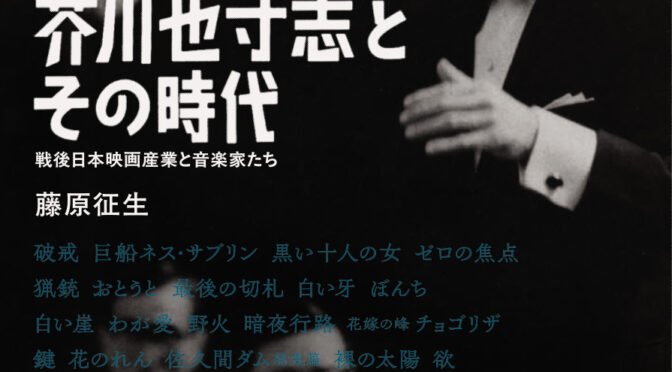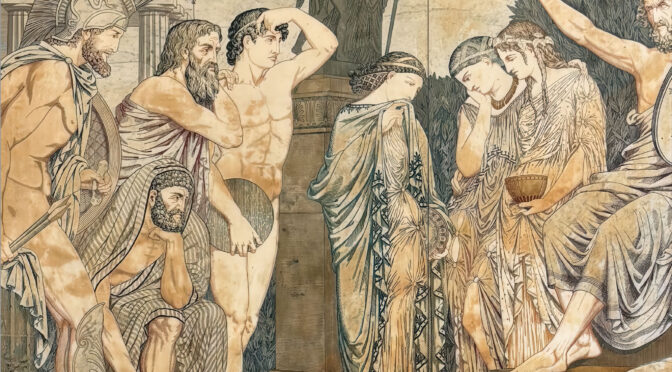林 政佑『帝国日本の監獄行政 植民地台湾と朝鮮を中心に』
2025.08.10
著者:林 政佑(台湾輔仁大学法学部 副教授)
出版社:京都大学学術出版会
発行年月日:2025年3月24日

書籍紹介
本書は、帝国日本による植民地支配下にあった台湾と朝鮮における近代的監獄制度を比較検討し、さらに両地域の制度的異同とその要因を明らかにすることを目的とする。帝国日本の近代監獄について、帝国史の観点から日本内地と植民地との連関を考察し、監獄がいかに帝国日本における統合と排除の機能を担っていたのかを問題とする。本書は台湾と朝鮮の監獄をめぐる「法制・言説・運用実態」という法社会史の研究方法による三つの位相に着目し、植民地主義のみならず、近代的刑罰というもうひとつの軸を加える必要があるという考えに基づき、台湾・朝鮮の監獄行政を分析したものである。
第1章では、植民地朝鮮と台湾の監獄教誨制度とその運用について考察する。具体的には、監獄教誨に関する法制を概観すると、植民地の台湾と朝鮮では、日本内地の監獄法に依って定められ、施行されていった。しかし、昭和期の教育刑の現れと見なされる行刑累進処遇制度は、制度的な落差が存在していたことがわかる。教誨師の構成は日本内地と同様に、植民地朝鮮及び台湾でも浄土真宗が独占した。教化の実践面については、植民地での教誨は、言葉の壁や現地の宗教を取り入れなかったことなどにより挫折することもあった。
第2章と第3章では、それぞれ植民地台湾と朝鮮の監獄労働作業について明らかにする。両植民地では植民地統治を通じて監獄作業の制度と業種が定着していったが、それは監獄運営の自給自足という観点と密接にかかわっていた。台湾の監獄作業は主に官司業だったが、朝鮮における監獄作業は受負業や構外作業への依存度が比較的高かった。満洲事変以後、官司業と中央の統制が一層強化された。また、朝鮮の監獄作業の自給率は日本内地及び台湾より低かった。植民地の受刑者の賃金などが内地に比べてはるかに安かったことは、植民地主義の現れと考えられる。このように、植民地監獄が収容者にどのように作業をさせたのかについて、また、作業の目的と種類、時期による変化及び意義について論じる。
第4章では、植民地朝鮮と台湾の看守戒護について考察し、看守の養成、民族別の構成などを明らかにし、看守と受刑者との関係から、植民地の監獄の文明化と暴力の問題を論じる。近代的監獄行刑は文明化という理念を高く揚げて、近代法によって刑罰の暴力は制限されることとなるが、史料などから看守が収容者に暴力を振るっていたことは明らかである。その暴力は異なる民族の間で生じていたのか、すなわち、植民地性の表れだったのかという問題について見ると、両植民地における看守を民族別に見ると、朝鮮では朝鮮人の看守が四割程度を占めていたが、台湾では台湾人の看守は極めて少数であった。同民族の朝鮮人看守と朝鮮人収容者の間でも暴力が振るわれていたことから、植民地の差別のみならず、刑罰執行の権力を持つ者と受刑者との社会的距離や排除という要因も看過できないことが示された。
第5章では、植民地朝鮮と台湾における司法保護制度とその運用について考察し、司法保護制度が監獄と外部社会をどのように連携させ、出所者が社会でどのような状況に遭遇するかを探究する。司法保護事業は当初、慈善事業として始まり、監獄職員や関連団体が各地方の司法保護組織を設立した。監獄職員などは出獄者に職業訓練を提供したほか、自らが保証人になったり保証人として民間業者を紹介したりして出獄者の就職を促進した。戦時期には、総督府が日本内地の司法保護法を植民地に延長し、統制化を行い、人力の動員と教化を確保することになった。
結論では、植民地台湾及び朝鮮における監獄行刑について分析を行い、教誨、監獄作業、看守及び司法保護を研究課題として、植民地主義と近代的刑罰という二つの軸を駆使し、法制、それに関わる言説及び運用実態の三つの側面から考察した上で、両植民地統治の比較、刑罰理論、植民地統治及び近代法等に関する理論を検証する。
本書では、監獄制度と実践の比較を通じて、近代日本帝国の統治方式だけでなく、朝鮮と台湾という異なる植民地における統治の違いを探究できたものと考えている。監獄の運営からは、二つの植民地が形成された背景、経済状況、総督府の政策の違いなどが窺え、植民地統治の差異を描き出すことができた。また、本書では、植民地近代性(colonial modernity)理論との対話を行った。その際、確かに「植民地」と「近代」の二つの観点から植民地刑罰を検討することには意義があるが、「近代的」な部分では過度な抽象性という懸念があると考えられる。本書は、近代的監獄制度の比較検討においては、国際監獄会議などを通じた監獄行政に対する具体的な国際評価や、社会的な側面、例えば受刑者の監獄や自由刑に対する意識、監獄行政が有するインフラとしての側面などを組み合わせるべきだと主張し、それにより、植民地監獄の性格及び意義がより把握できるものと考える。