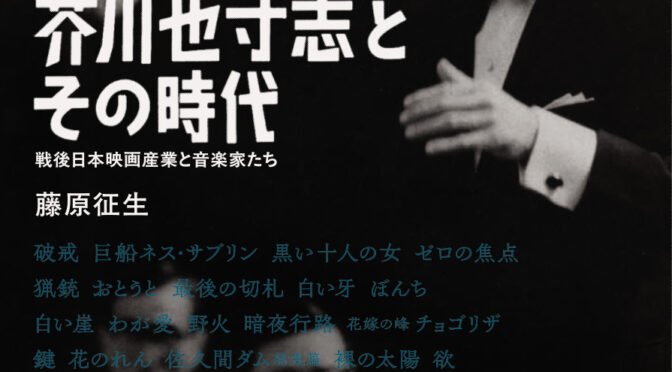浦井 聡『田辺元──社会的現実と救済の哲学──』
2024.10.25
著者:浦井 聡(日本学術振興会特別研究員PD(北海道大学))
出版社:京都大学学術出版会
発行年月日:2024年3月31日
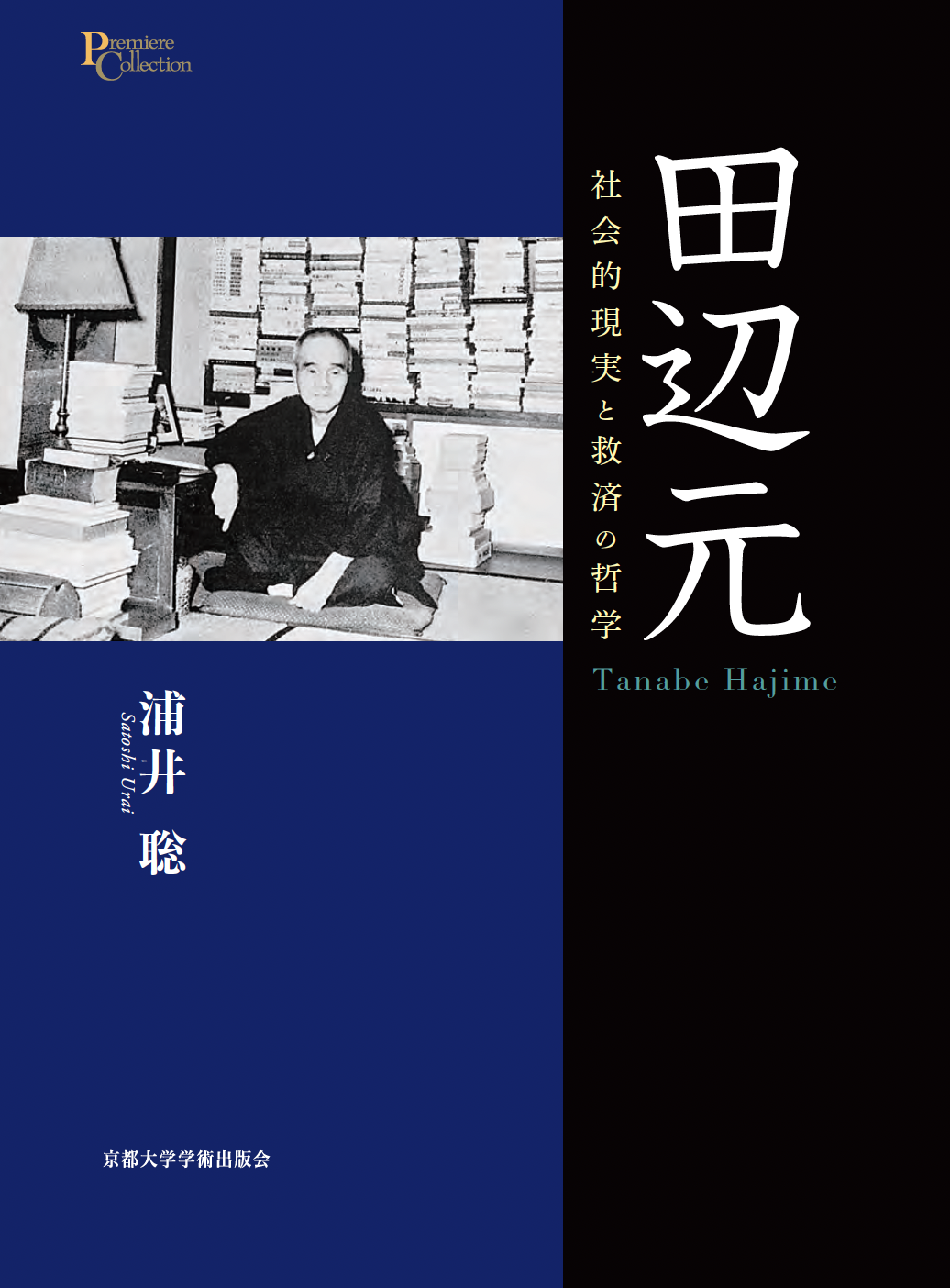
書籍紹介
何かが嫌だと感じるのはなぜなのだろうか。例えば、誰かが場違いな格好や仕草をしている時、敬語を使うべき関係性の相手が使わなかった時、土足禁止の場所に誰かが土足で上がった時、私たちは違和感を覚える。また、自分が不注意でそのような行動を取ってしまった時には居心地の悪さを感じる。この違和感・居心地の悪さはなぜ起こるのだろうか。
おそらく最も簡単な答えは「ルールを破っているから」だろう。だが、なぜルールを破ることに不快感が伴うのか。もちろんここで、ルールを守ることを擁護したいわけでも茶化したいわけでもない。問題にしたいのは、私たちが日常的にルールとすら呼べないものに、自分自身に利害関係がない場合であっても感情を左右されていることである。例えば、飲食店で誰かが店員に横柄な態度を取る姿を見て、店員が自分の知り合いでなくとも、えも言われぬ不快感を覚える人は決して少なくないはずである。しかし、言うまでもなく誰かが店員にある程度横柄な態度を取ることは法律で禁止されているわけではないし、その出来事によって自分自身に不利益が生じるわけでもない。それでも不快感を覚えるのだから、その原因となっている何かあるはずである。では、その「何か」の正体は一体何だろうか。
本書の主題であり京都学派を代表する哲学者、田辺元(1885-1962年)はその正体を「種」と呼んだ。この文脈での種は、平易に言えば私たちに宿っている〈内なる社会〉である。つまり、私たちが社会の中で生まれ育つ過程で自然と身につけた価値観が〈内なる社会〉として常に私たちの思考に介在していると田辺は考えた。だが、これはどういうことだろうか。
先ほどの店員の例で考えてみよう。これは文章にすれば「店員に横柄な態度を取ることは私にとって不快である」と表現できるだろう。このことに〈なぜ?〉と問う時、その理由が必要になる。例えば「店員が可哀想だから」というようなものである。この理由を加えると「店員に横柄な態度を取ると店員が可哀想である」、「店員が可哀想であることは私にとって不快である」、だから「店員に横柄な態度を取ることは私にとって不快である」ということになる。だがこの説明もやはり不十分であり、それぞれに理由が必要となる。つまり、「店員に横柄な態度を取ると[Xだから]店員が可哀想である」、「店員が可哀想であることは[Yだから]私にとって不快である」という形で理由が必要となる。しかし、おそらくこのXとYに何を入れてもそれだけで自明な説明──例えば物理法則のような──にはならず、さらに別の理由を必要とする。そして理由によって説明されたそれぞれの文章がさらに別の理由を必要とし、理由を求める運動は繰り返され続ける。
このように「店員に横柄な態度を取ることは私にとって不快である」という私たちが現に体験する日常的な出来事を説明するために可能的に無限な理由を必要とする。だが、実際にはどこかの時点で理由を考えられなくなって〈正しいことは正しいから正しい〉〈悪いことは悪いから悪い〉というような同語反復を理由としているのが実情であろう(例えば「横柄な態度は不快だから不快である」)。そうであれば、私たちの思考はその根底において〈正しさ〉を保証する理由を持たないことになってしまう。そこで田辺は私たちの思考を規定するものとして私たちの〈内なる社会〉を位置づけた。これが〈正しいことは正しいから正しい〉というようなそれ自体で内容を持たない考えすらも可能にしている。別の言い方をすれば、私たちのあらゆる思考は私たちの〈内なる社会〉から常に影響を受けて成立しており、自分がいかに自由に思考をしていると思っていたとしてもそれは幻想に過ぎないと田辺は考えたのである。
だとすれば、私たちが日々何かを正しい/悪いと判断しているその瞬間に私たちは〈内なる社会〉にそう考えさせられていることになる。何かを〈正しい〉と確信すればするほど、私たちは〈内なる社会〉の操り人形となり、その代行者として行動していることになる。〈正しい〉態度、〈正しい〉考え、〈正しい〉行動──これらはすべて〈内なる社会〉が規定する〈正しさ〉の実現でしかない。仮に「理性的」や「進歩的」と見なされるような〈正しい〉立場があったとしても、その立場を振りかざすだけでは〈内なる社会〉の代行者として別の〈正しい〉立場と終わらない争いを続けることになる。そこではいかなる「理性的」「進歩的」な立場も実際には「理性的」「進歩的」という名の下で行われる本能的な反射行動のようなものではないだろうか。
では、私たちはいかにこの争いから離れ、真に自由に思考することができるようになるのであろうか、そして社会の中で常に社会から影響を受けて生きている私たちにとって真に自由な思考・行動とは何か──田辺哲学の核となる社会存在論はまさにこの問いを扱ったものである。
田辺は1934年から社会存在論を世に問い始める。当初は多くの人たちが理性的に思考し、行動するようになりさえすれば社会は善くなっていくと考えていた。だが、この素朴な考えは10年も経たず戦争の進展と共に打ち砕かれる。この挫折の後で、田辺は宗教的な地平を織り込んだ社会存在論を構築し、これによってこそ互いに害し合う人間が共に生きていくことが出来ると示した。本書は、この田辺の企ての全体像を明らかにしたものである。