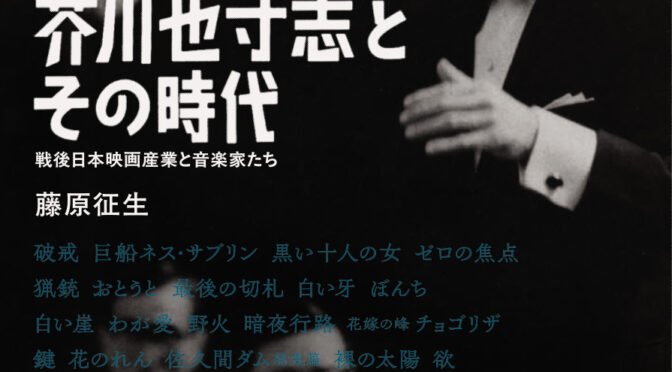陳 佑真『三蘇蜀学の研究――北宋士大夫による儒家経典解釈の展開』
2024.10.22
書籍紹介
本書は、詩人としてきわめて高名な中国北宋の蘇軾やその父・蘇洵、弟・蘇轍の儒学思想を対象に研究したものである。
蘇軾といえば、「赤壁の賦」や「黄州寒食詩巻」といった名作により中国文学・芸術の世界に金字塔を打ち建てた人物として広く名を知られている。だが、そんな彼自身が最晩年、自らの生涯も無駄ではなかったと思わせてくれる業績は『論語』・『周易』・『尚書』の注釈であり、他には何もない、と述べていることはあまり知られていない(『東坡続集』巻七・答蘇伯固・第二簡)。
蘇軾自身がそのように自賛した経書の注釈書は、あるいは明代後期に蘇軾ブームが起こるまで一部の愛好家を除いて顧みられず、あるいは散逸して諸書に断片が引用される形で伝わるにすぎず、その詩文が絶えず多数の読者を得て議論の的となってきたのに比してその研究はあまりにも少ない。
本書が取り扱う経書解釈学(経学)には、唐の五経正義に代表される古注、そして宋の朱熹やその一門の著作に代表される新注という二つの大きな流派が存在する。五経正義は緻密な論証に基づいて経書本文や漢・晋の注釈の説を解明したものであり、高い完成度を誇る。にもかかわらず、それは宋代に至って新注によって反駁されねばならなかった。その背景にあるのは、宋代における士大夫政治の確立である。
科挙によって選抜された士大夫がその儒学の学識に基づいて政治を実行するのが、宋という新たな時代の特色である。彼ら士大夫階層の存立の根拠となったのは貴族社会の家柄ではなく、聖人の述作に係る経書の知識であった。「経」とは「道の常」(『春秋左氏伝』昭公二十五年伝・杜預集解)であり、時代を問わず普遍的に通用するものでなくてはならない。仮に経書の内容が宋代の現状に合致しないように見えたのであれば、それは経書そのものではなく解釈者の過失なのであり、その時々の現実に当てはまるより「正確な」読解を行うことが士大夫の責務であった。
詩人として己の心情を歌い上げ注目を集めた蘇軾らも、その根本は士大夫であり、それゆえその本業としての経書解釈に真剣に向き合い、それを思想の核としながら文学的作風を確立した。かかる事情から、中国宋代の思想や歴史に関心をおもちの方はもとより、蘇軾らの詩文や芸術方面の功績に関心をおもちの方、また、広く政治思想に関心をおもちの方にも本書をお手に取っていただければ幸いである。
以下、蘇軾らがその士大夫意識に基づいて各経書をどのように読んだか、かいつまんで紹介する。
(1)『周易』について
蘇軾の『周易』解釈の重要な特徴は、注疏以来の義理易の立場を採りつつ、当時顧みられることの少なかった象数易の観点を多く導入していることである。
蘇軾は一卦を構成する六つの爻について、それらの間の関係に関心を向け、婚姻をモティーフとした解釈など独自の説を展開した。また、『周易』の術語に対する解釈の不徹底という当時の義理易のもつ問題点を自覚し、一書を通じた法則性を確立することに心血を注いだ。こうした姿勢は、蘇洵以来の「数」への畏敬に端を発するものである。
(2)『尚書』について
蘇軾は『尚書』を理想的な政治のあり方を述べた書として見る姿勢を徹底し、多く宋代の現実社会の問題と結びつけて解釈した。
とりわけ、禹貢に見られる僻地の納税の問題や、呂刑に見られる取り調べにおける自白の利用の問題に着目した注釈などは宋代の社会現実に対する蘇軾の問題意識を如実に反映したものであり、士大夫としての責任感をそこに見出すことができる。ほか、堯典への注釈で冬の早起きは農民にとっても困難だ、などと述べるところからはその民衆に寄り添う細やかな心配りを感じさせる。
こうした蘇軾の説は南宋の蔡沈『書集伝』にも多く採用されたが、社会現実に切り込んだ部分はあまり使われなかった。このことは、蘇軾らの蜀学と道学との指向の差異を示唆している。
(3)『論語』について
北宋では、性善説の立場から、善である未発の性への回帰を唱える李翺の説が流行した。李翺は情を取り除いて性へ回帰する手段として『詩経』や『論語』に見える「思無邪(思ひ邪無し)」を挙げるが、蘇軾兄弟はこの「思無邪」についてそれぞれ独自の解釈を行った。
蘇軾は「思無邪」に至るために必要な方法として、書を読み尽くし、考え尽くすことを『楞厳経』から着想した上で提唱する。一方で蘇轍は、仏説を導入せずあくまでも儒家思想の範疇において「思無邪」を理解しようとした。そこには蘇軾に見られる復性説への拒絶は見受けられず、性善説に同調することを避ける一方でむしろ復性説に近い論理展開を示している。
蘇軾兄弟は、一方は仏説を儒家の経典解釈に取り入れることの容認、一方は復性説的論理の導入と、異なる修養像を展開したのであるが、その共通点として重要なのは性善説への拒否である。
蘇軾らの経学がのちに道学に圧倒された最大の要因はこの性善説への拒否にある。唐代貴族社会の家柄の枠組みから「解放」されて世界に投げ出された知識青年たちにとって、程頤ら道学の大家が示した性善説に立脚した「聖人可学」説、『大学』八条目はきわめて魅力的に映り、それが南宋における道学の隆盛につながった。
しかしながら、蘇軾はそのような無邪気な性善説の展開がもつ危険性、すなわち聖人を目指す、という道学が考えたあるべき学問のモデルが絶対視されることによって生き方の多様性が軽視されかねないことに気づいていた。性善説への拒否という形で警鐘を鳴らし続けていた蘇軾の経学が後継者を得ず埋没する結果に終わったのはあらがい難い世の趨勢といえようか。
(4)『孟子』について
三蘇、特に蘇軾は、孟子に対する批判的乃至懐疑的な主張を展開した知識人の代表格という扱いを受けてきた。しかし、この論調は、道学の「聖人可学」論の根底をなす性善説に蘇軾や蘇轍が同調しなかったことを南宋の朱熹や余允文が大きく取り上げて非難した結果であり、実際には蘇軾らは孟子の書を学習対象として大いに重んじ、孟子の思想を元に様々な議論を展開していた。
蘇洵は『孟子』の文学的価値を非常に高く評価し、韓愈や欧陽脩に並ぶ文学者であるとする。また、思想方面でも『諡法』などにその影響を伺うことができる。蘇軾は孟子を禹と並べ称しており、蘇轍は諸家の雑多な説を弁別するための柱として孟子を扱う。
とりわけ蘇轍における『孟子』の重要性は顕著で、蘇轍はその『孟子解』の中で、人々の欲求に応じて文明が漸進的に進歩する、という文明観や、道徳性と天下統一の成敗は無関係である、という歴史観を提示した。こうした意見は、正統論争など当時の重要な思想界のトピックとも結びついている。