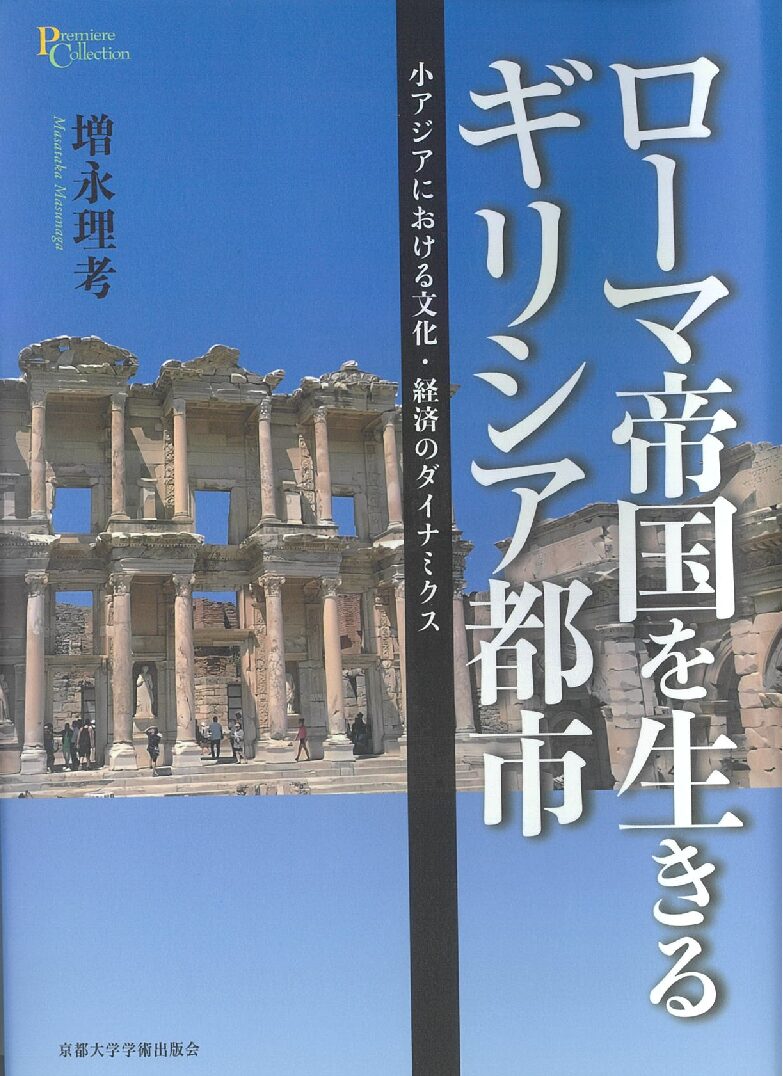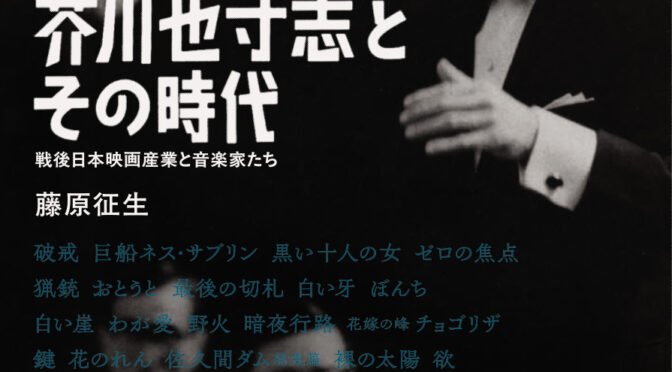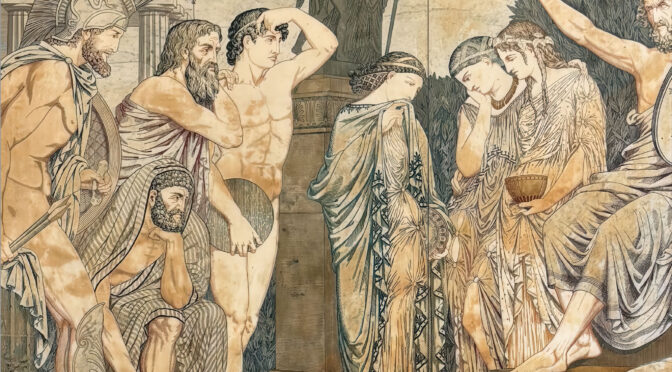増永 理考『ローマ帝国を生きるギリシア都市――小アジアにおける文化・経済のダイナミクス』
2024.10.15
書籍紹介
およそ2000年前、地中海規模で領域を拡大した古代ローマ帝国だが、その支配下にはかつての古代ギリシア文明が栄えた地域も含まれていた。ギリシア人の共同体は、ローマ帝国統治下でも、東地中海一帯で既存の都市(ポリス)的生活を存続させていたのだが、このようにローマに包摂されたギリシア人社会の帰趨は少なくとも我が国ではほとんど知られていないだろうか。では、以上のようなギリシア人たちは、
この問題をめぐって、本書は、前1世紀末~3世紀末に相当するローマ帝政前期、ギリシア的社会が拡大していた小アジア(現トルコ)を対象とし、その地域の諸都市の運営・発展に不可欠であった都市有力者による恵与を切り口として検討している。以下、その理由も含めて、本書の背景をもう少し具体的に明らかにしておこう。
従来、ローマ帝国配下のギリシア語圏における諸都市は、政治的独立を喪失し、次第に衰退したと理解されてきた。しかし、欧米を中心とする近年の学界では、ポリス存立に関わる定義の見直しや、考古学調査の進展に伴う史資料の増加を契機として、ローマ支配以前のヘレニズム期以降、「ギリシア化」が著しかった小アジアを中心に、諸都市が有する活力の継続が強調されている。
こうした評価の転機に重要な影響を与えたのが、恵与慣行(エヴェルジェティスム)に関する研究である。これは、都市有力者が、共同体に食料や建築物などを私費で提供する慣行を指すものとして、20世紀末より学界に流布している分析概念であるが、これを扱った研究では、「与える」という行為自体や恵与者に主眼が置かれ、ことローマ帝政期に関しては、その前期を一枚岩として、有力者にとっての公的恵与の意義をめぐる議論が展開されてきた。だが、それらを享受する都市共同体は恵与者と交渉し、恵与物の傾向自体も変化していたため、都市にとっての恵与の意義とその変遷も追究されなければならない。
この課題に取り組むべく、本書は、ギリシア都市の動向を見直す契機となった小アジア、特にその西半の都市を対象に、恵与として隆盛した公共建築物と祝祭の動向に着目する。これらは、都市全体に包括的な影響を及ぼした一方、2世紀以降、その流行が建築物から祝祭へ傾くことから、受益者たる都市共同体に付加される恵与の価値を動態的に跡づける上で最適な対象と考えられるからである。
他方、ローマ帝国統治下の諸都市をめぐっては、2世紀以降、帝国から金銭の拠出を強いられた有力者層が窮乏した結果、彼らの恵与に依拠していた都市は次第に凋落した、と理解されてきた。帝国に従属する有力者らの動向に主眼を置くこの都市像に対しても、本書は、有力者に限定されない都市共同体全体の観点から見直しを迫る。
このように本書は、都市と、そこで行われた文化的、経済的意義を有する恵与を軸に、ギリシア都市社会とそれに対するローマ帝国支配のダイナミクスを、帝政前期という時間軸のなかで描き出すものとなっている。
小アジアの都市に由来する多数のギリシア語碑文史料、特に、公的恵与に関する顕彰碑文や奉献碑文、恵与を実施した有力者に関する文学的史料、恵与の規制をめぐる法文、さらには恵与物を描いた貨幣という多彩な素材を基に、本書は次のことを明らかにしている。すなわち、ローマ帝国の支配下という一定の限界を有しながらも、ギリシア都市社会は競合的に名誉や経済的利益を求め、地域的文脈の中で恵与を運用する能動性や柔軟性を発揮していたのである。本書は最終的に、ローマ帝国に服従しながらも、ときに彼らを利用しつつ、ローカルな社会を自律的に生きるギリシア都市の姿を浮き彫りにし、都市有力者の視点を中心とした従来の単なる支配―従属の二項対立的図式では捉えることのできない、帝国と都市の複雑な関係と、その中でダイナミックに推移するギリシア都市共同体の歴史像を提示している。
ヘレニズム期以降、とくにローマ支配下のギリシア人世界をめぐる研究に関しては、欧米とは対照的に、日本での成果蓄積は決して十分であるとはいえない。ギリシア史、ローマ史にまたがる本書が今後の研究の踏み台となり、西洋古代史全体で議論が活発化するための一つのきっかけとなることを筆者は願ってやまない。