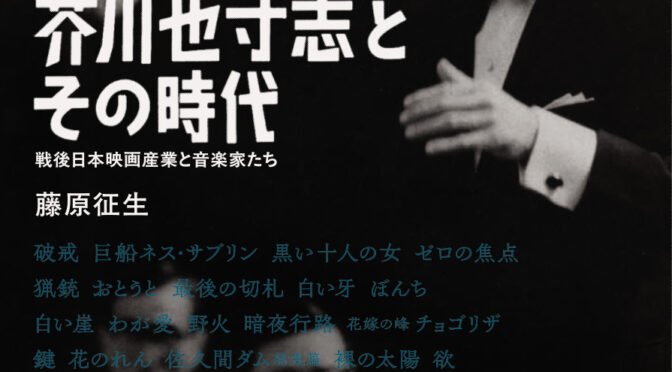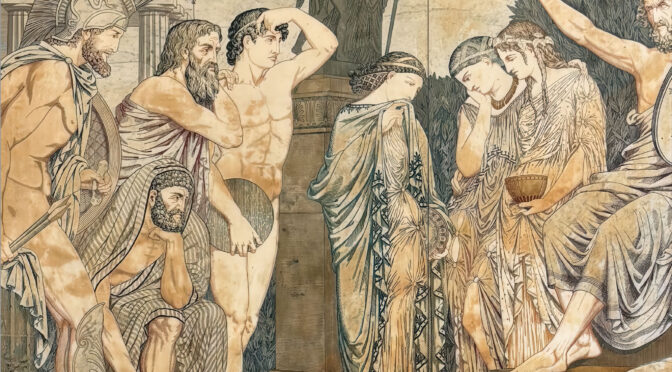石谷 慎『春秋戦国時代の青銅器と鏡 ―生産・流通の変容と工人の系譜』
2024.10.15
著者:石谷 慎(京都府立大学文学部 共同研究員)
出版社:京都大学学術出版会
発行年月日:2024年3月31日

書籍紹介
春秋時代(紀元前770年~前453年)には、周王室に代わって斉や晋などの諸侯国が覇権を握り、有力諸侯国が小国を併合しながら領域を拡大していった。その結果、戦国時代(前453年~前221年)には韓・魏・趙・斉・燕・楚・秦の七国が覇を争い、やがて秦が武力によって天下を統一する。そんな激動の春秋戦国時代は、政治史のみならず文化史においても分裂と対立の時代として評価され がちである。
実際、これまでの春秋戦国時代の青銅器研究は、諸侯国単位もしくは地域単位に行われることが多かった。しかし、たしかにこの時代の青銅器には「国別」と呼ばれる国ごとの個性や、中原・山東・華中などいくつかの国を包括する範囲での地域性が見られる一方で、ある国でつくられた器が遠く離れた別の国から出土したり、地方の小国でつくられた器に中央の大国の器とそっくりな紋様が見られたり、ということが少なくない。
本書は、そんな春秋戦国時代の青銅器文化の「複雑さ」に目をつけ、中国各地の諸侯国墓から出土した青銅器や鏡などの青銅製品とそれをつくるための鋳型や原型などの生産関連遺物の考古学的検討、および文献・青銅器銘文に見られる工人や生産組織に関する記述との対照を通して、国や地域の枠を越えた面的な生産・流通の総合的な解明を目指したものである。ここでは、副題でもある「工人の系譜」を問題にとりあげ、本書の内容を紹介したい。
「工人」とは、辞書には「工作を職とする人」と説明されるが、その実態はどの程度明らかだろうか?青銅器づくりには、粘土をこねて原型(模型)部品をつくり、それらを基に鋳型部品を起こし、複数の鋳型部品を組み合わせて器全体の鋳型をつくり、溶かした青銅の湯を流し込んで鋳造する、というような、いくつかの工程が存在する。このように複雑な青銅器生産の場において、いったい工人とはどのような技術を有し、どのような作業に従事した者を言うのだろうか?
実は、戦国時代の工人については、歴史文献や青銅器銘文から多くのことが明らかとなっている。例えば、『礼記』や『荀子』には、末端工人の「工」を監督する「百工」の存在や、それらをさらに監督し、不良品や不正の発生を防ぐ目的で置かれた「工師」の役割が見える。戦国時代の韓でつくられた青銅武器には、県令の韓熙という人物の監督下で武器庫兼製造所である右庫の「工師」が「冶」と呼ばれる末端工人を監督したと明記されている。なかには「司寇」という刑罰をつかさどる官職や「鬼薪工」「工隷臣」といった刑徒・奴隷の名が記されることもある。戦国時代には、「工人」にも様々な身分があり、組織的な分業体制のなかで青銅器づくりに従事していたと知られる。
一方で、春秋時代の工人については、まだまだ不明な点が多い。早くも1960年代には晋都新田の青銅器生産を担ったと思しき侯馬鋳銅遺跡の大発見があったが、戦国時代のように生産に携わった工人の名は確認されなかった。ただし、侯馬からは青銅器づくりに使用された多くの鋳型や原型が出土しており、本書ではそれらの紋様観察と遺構ごとの組合せ分析を通して、異なる紋様表現の鋳型や原型が同一遺構から出土している実態を明らかにした。つまり、侯馬では原型や鋳型の部品ごとに異なる工人によって製作が行われ、しかも工人によって出自が異なった可能性が高いのである。それは同時に、春秋時代の晋の青銅器工房においても戦国時代の「工師」や「冶」に相当する身分差があり、製造工程による組織的分業が行われた可能性を示している。
ところで、西周時代以来、王朝は淮域(淮河流域)の銅資源を獲得する機会を諸侯に分配することで、服属を確保していたと知られている。春秋時代のはじめの頃には、淮域の小国で時代を特徴づける「螭紋」を施した青銅器が生産され、半ば以降には中原諸国にも広まっていった。侯馬で生産された青銅器にも淮域の青銅器と共通する紋様表現が多数確認される。淮域に出自する工人を取り込み、その青銅器生産を継承することが、王室に代わって主導権を握る覇業であったのだろう。さらに戦国時代になると、侯馬で行われたのと同様の鋳型や原型の部品を駆使した青銅器生産が南方の楚でも行われ、侯馬の技術が持ちこまれた可能性、つまりは晋から楚へと工人が移動した可能性がうかがえる。工人の系譜は、淮域から晋へ、さらに晋から戦国時代の諸侯国へと連なった。
戦国時代の半ば以降には青銅礼器の生産が衰落し、華美な装飾を施す青銅器は求められなくなる。大量生産の仕組みが秦の官営手工業へと引き継がれる一方で、侯馬や楚都江陵の青銅器生産に見られた高度な鋳型づくりの技術は必要とされなくなるが、その技術は秦漢時代の手工業の基盤となる民間での銅鏡生産や瓦当づくりなどにうかがえる。「技術」に注目することで、春秋戦国時代から統一王朝の時代へと続く「工人の系譜」が浮かび上がるのだ。