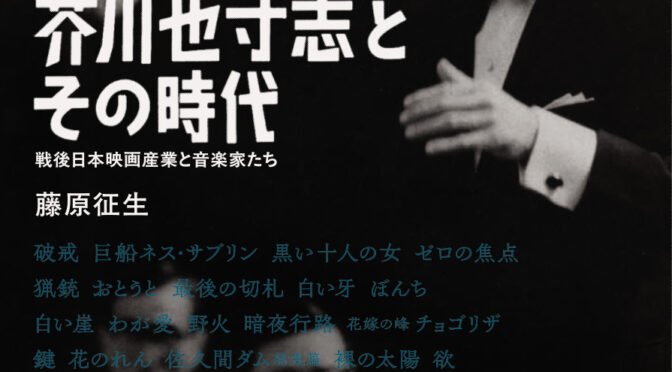奥井 剛『ハンナ・アーレントの政治哲学の射程――開発という活動の再考に向けて』
2024.11.06
著者:奥井 剛(京都大学特定研究員)
出版社:春風社
発行年月日:2024年4月8日
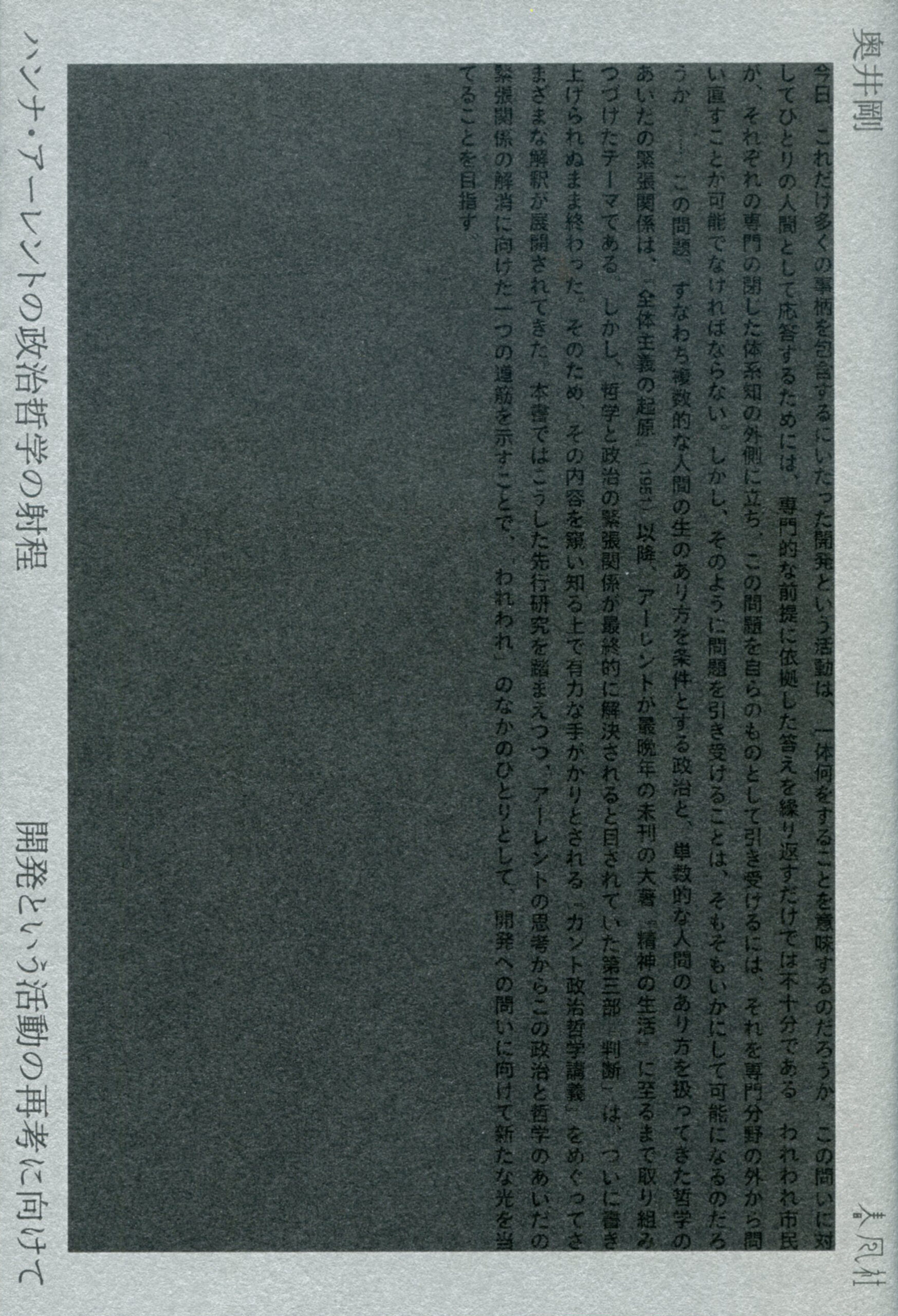
書籍紹介
今日、地球規模で展開されている開発という活動は、持続的な人間の生のあり方を脅かしつつあります。本書はハンナ・アーレント(1906-1975)の政治哲学を導きの糸として、この活動が人間にとって一体何を意味するのかを再考するひとつの道筋を示しました。
「開発(develop)」という言葉の語源は古仏語にあり、もともと覆われた何かを「開示すること」を意味しました。この語は中世の騎士道文学にすでに見られ、ルネサンス期においても語源的な意味を湛えていましたが、啓蒙主義時代に入ると「進歩」の概念と強く結び付くようになります。さらに近代生物学の黎明期において生物学的な「発生」や「成長」を表す言葉として用いられるようになり、それが再び社会科学へと再び持ちこまれることで、経済的成長あるいは生産量の増大と結びつけられるようになりました。この意味での開発という活動を通して、いまや人類はさらなる開発へと互いに駆り立て合いながら、経済的な関心によって覆い尽くし、地球を貪り尽くそうとしています。
本書では「開発」を再考するために、アーレントの政治哲学を手がかりに「開示すること」はわれわれにとって何を意味するのかを探究しました。彼女は主著の『人間の条件』で、われわれの活動を行為(action)、制作(work)、労働(labor)に区別しました。制作や労働は人と物の関係に関わりますが、行為は人と人のあいだの出来事に関わります。つまりわれわれは、行為することで、自分がいったい「誰」であるのかを、われわれが共に住む世界へと「開示する」のです。一方で彼女は、思考も一種の活動であると述べていました。ただし「一者のなかの二者の対話」ともいえる思考は、世界から退くことを必要とします。つまり行為と思考は緊張関係にあります。
この問題は、彼女の最晩年の未完の大著『精神の生』の第三部「判断」で取り組まれるはずでした。その第三部の内容をうかがい知る上で『カント政治哲学講義録』(『カント講義』)が有力な手掛かりとなります。本書では、そこで展開された「判断すること」の意味をテクストに即して跡付けることで、言論を通じて結びつく両者の関係を一つの連関において描き出しました。
そこから見えてくるのは、世界のなかで起きる問題について考え、言論を通して互いに意見を表し、共に行為することで開示する「われわれ」の姿であり、われわれが共に生きる持続的な世界のあり方です。開発の根幹に据えられるべきは、そのような「われわれ」を開示する行為であると言えるでしょう。
植民地主義から帝国主義の時代へと移り変わる十九世紀末に、ゴーギャンは孤独のなかで「われわれはどこから来たのか、われわれは何者か、われわれはどこへ行くのか」と題された絵を描きました。現代に生きる皆さんの目には「われわれ」はどう映るでしょうか。
本書には筆者の不手際により付すことのできなかった短い結論があります。この場を借りて以下にそれを記したいと思います。
結論 開示するわれわれ
開発は、いっけん茫漠としていてつかみどころがない。しかし開発もわれわれの活動である以上、その活動そのものに向き合わずに、そこから生じるさまざまな問題に対して技術的に対処するだけでは、問題の根本的な応答にはなり得ない。その端緒を開くためには、そもそも開発という活動によって、われわれは一体何をしているのかという問いが、問い直されなければならないのである。そのために、既存の知の枠組みを超えて現実の問題に応答する総合的な学術が要請されている。その試みがたんに分断された知識の総動員にとどまらないためには、問題の新たな理解の可能性に向けて諸分野で培われたそれらの知識をひもとき、再び編みなおす人文学の役割が不可欠となる。
それだけでなく、さらにその学術の営みを実践へと、すなわち――たんに専門家と官僚を介して政策に結びつけるのではなく――複数で生きるわれわれの行為へと取り戻す道筋が示されなければならない。とはいえ、われわれはもはや、観想的生を理想として一者の観点から絶対的な真理を観取し、その尺度に政治を従わせしようとした西洋哲学の伝統の立場に戻ることはできない。実践をその射程に据えた新たな総合学術の試みを、伝統の立場から撥ねつけるのでもなく、はたまたそこに再び引きつけようとするのでもなく、われわれの新たな人文学のあり方として迎えることができれば、地球規模で進展するこの未曽有の危機に向き合い、その知をわれわれの行為へともたらし得る日が来るかも知れない。開発の再検討に向けてその展望を示すこと、これこそ本書が試みたことに他ならない。
第一章では、開発という活動を理解する糸口として、開発の意味の探求へと向かった。開発の語源は、その響きの中に「開示する」という意味を湛える。その意味への問いは、ハイデガーとアーレントの開示をめぐる立場の違いをめぐって鮮明になる、哲学と政治の間の緊張関係という袋小路に行き当たる。この問題は、古代ギリシアにおける哲学と政治の対立に端を発するが、現代に至ってもなお、思考することと行為することの間の深淵へとその巨大な陰を投げかけ続けている。
生涯をかけてこの問題に取り組んだアーレントは、「新しい政治哲学」の誕生に期待を寄せていた。そこで彼女の思索が最後にたどり着いた「判断」という概念がその可能性へと投げかける光芒をたよりに、第二章では『カント講義』を詳細に跡付けた。その途上でおぼろげに輪郭を顕し始めるのは、言論を介して思考と行為を結び合わせる判断の豊かな可能性であり、世界の中で共に言葉を交わし合い、共に行為しようとするわれわれの新たな共生のあり方へと向けられた、彼女の政治哲学の射程である。
アーレントは『カント講義』の最終講義で、カントの「根源的契約の理念」および「範例」を扱った。カントがそうしたように、「根源的契約」が単なる「理念」に留まる限り、それがわれわれの眼前に現れることはない。しかし、もしそれが現実として起こった事実であったなら、われわれはそれを「範例」として判断することができる。メイフラワー誓約という約束の行為から始まったアメリカ革命がアーレントを驚嘆させたのも、それが範例となりアメリカ建国への道を開いたという事実にある。第三節で考察したのは、こうした範例の実践的意義である。事例として、筆者が実務者として携わったUNESCOの世界人文学会議と、バングラデシュの農村における評議会制度から得られた経験と洞察を振り返り、その視線の中に現れた光景を最後に記した。
そこに現れたのは、ホメロスが描いたアキレウスの盾の装飾を彷彿とさせる情景の中で、共に集い、世界を愛しむその眼差しのなかに出来事を捉え、人々のなしうる偉大な行為に思いを馳せ、言論を通してすぐれた行為と判断を称え合い、自由の領域を守るために約束を交わす「われわれ」であった。リエージュ大学で世界人文学会議の成果文書が採択されたとき、あるいはバングラデシュの農村の評議会で用水路に橋を架ける計画が合意されたとき、もし本書の読者がそこに居合わせることができたならば、新たな「われわれ」のあり方の可能性を感じずにはいられなかっただろう。そして、もし本書を通してその経験を共にしてくれたのなら、こう考えるのではないだろうか。われわれが自らを開示する行為こそ、開発という活動の中心に据えられなければならない、と。