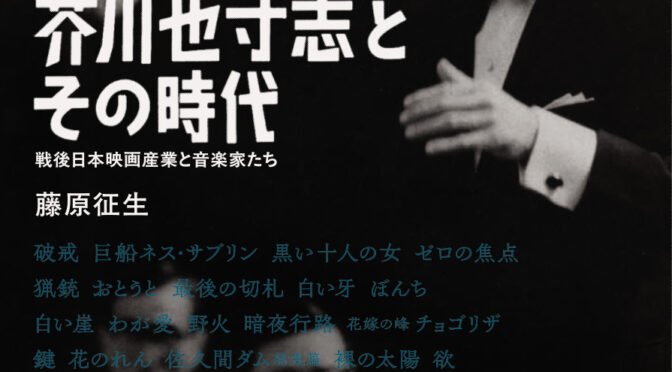中村 徳仁『シェリング政治哲学研究序説:反政治の黙示録を書く者』
2025.08.16
著者:中村 徳仁(三重大学 助教)
出版社:人文書院
発行年月日:2025年3月20日

書籍紹介
F・W・J・シェリング(1775~1854 年)はこれまで、ヘーゲルをはじめとした同時代の知識人たちと比べると、政治哲学の文脈であまり論じられてこなかった。本書の目的は、そのようにして軽視されてきたかれの思想のなかに政治哲学を見出し、その固有性を「反政治 Antipolitik」という概念によって特徴づけることにある。本書は「まえがき」「序論」、4つの章で構成される「本論」、そして「結論」から成る。
「序論:正統と革命のはざまに立つシェリング—先行研究の整理」では、1950 年代後半から2010 年代にかけての研究史を4つの時期にわけて再構成し、先行研究の問題点を指摘したうえで、本研究の問題設定と主要テーゼを提示する。そこでも確認されるように、シェリングの政治論や国家論は、大学論や宗教、芸術などといった一見すると別の領域について論じているなかで、それらへの「付論」として論じられることが多い。そのため、シェリングの政治哲学を考察する際には、政治や国家について直接言及している箇所だけでなく、かれ自身の生きた時代に対する問題意識や、同時代人との論争、思想形成史、哲学的前提が措定されねばならない。その点が、本稿の「第1章」と「第2章」で深められる。
「第1章:新しい神話とその前史—若き日のシェリングを取り巻く言説状況」では、シェリングの思想形成に時代が与えた影響について考察する。かれが生きた 19 世紀前半の時代を、産業革命やフランス革命といった政治史・社会史的背景と啓蒙主義やロマン主義・敬虔主義といった思想史的背景をもとに特徴づける。なかでも重要なのは、この時代にはまさに、宗教をはじめとする中世以来の権威が根本から否定されると同時に、それに対する反動も激しく起こっていたということである。シェリングはそのような時代の揺れ動きを、敬虔主義を信じる家系とテュービンゲンの神学院において実体験することで、みずからの思考の根本を育んだことが確認される。
次に、「第2章:ラディカルに開かれた「同一性」をめぐる思考—完成と個性とのあいだの葛藤」では、『独断主義と批判主義にかんする哲学書簡』(1795 年頃)や『哲学と宗教』(1804年)、『人間的自由の本質』(1809 年)、そして「学としての哲学の本性について」(1820 年頃)といった、初期から中期にかけての主要な仕事を時代順に概観することで、シェリングの哲学がいかに両義性に開かれたものであったかを再構成する。そこでは、啓蒙主義的な進歩(完成)とそれには還元されない唯一性(個体性)とのあいだに、あるいは、批判主義と独断主義とのあいだに、知と信仰とのあいだに、哲学と宗教とのあいだに深まった諸対立を架橋する自由な思索の可能性が試みられている。そうした企ては、シェリングによる「同一性」モチーフの絶えざる彫琢を通じて為されているということが明らかとなるだろう。この同一哲学的発想は、ヘーゲルによる批判をはじめ、哲学史上も批判されることが多いが、それは対立する両者のあいだの交渉を可能にするための条件であることがここでは喚起される。
以上の2章で確認するシェリングの哲学的前提をふまえたうえで、続く2つの章では、かれがより直接的に法や国家について論じている箇所(第3章)と、かれがそれらへの対抗として引き合いに出す「哲学と宗教」のあり方について論じている箇所(第4章)を読解する。
「第3章:国家の中の居心地悪さ—必要悪としての法と政治」では、シェリングが国家や政治について一定の分量で述べた箇所を、さまざまな著作を横断しながら網羅的に読解していく。具体的には、『自然法の新演繹』(1796/97 年)、『超越論的観念論の体系』(1800 年)、『学問研究の方法にかんする講義』(1803 年)、『シュトゥットガルト私講義』(1810 年)、『神話の哲学』(1840 年代以降)が順番に検討される。シェリングの政治論ないし国家論は、時代が経つにつれて保守的になっていったとして、「断絶」や「変化」によって特徴づけられることが多いが、本書ではむしろ、その「連続性」に目を向けたい。その変わらざるモチーフとは、政治や国家を完全に克服することはできない「必要悪」として認めつつも、その影響力が野放図に人間の生に浸透してくることに対して抵抗しようとする姿勢である。
「第4章:ケノーシス的終末論としての哲学的宗教—『啓示の哲学』の「未来」」では、後期の思索を代表する『啓示の哲学』について読解する。後期のシェリングが完成させようと取り組んだこのテクスト群は、青年ヘーゲル派による当時の批判もあいまって、シェリングの保守化を象徴する思索だとされてきたが、本書は、それに反批判を試みる昨今の研究に示唆を受けている。
それらの研究は、後期シェリングに潜むユートピア主義ないし終末論的発想のなかに、政治からの解放のモチーフを見て取っている。ただし本書では、そうした評価に影響を受けつつも、かれの晩年の構想である「哲学的宗教」とかれが用いた「ケノーシス」という概念に注目して、先行者たちがあまり注目してこなかった『啓示の哲学』の箇所を読解していく。
そして最後に「結論」では、本論の内容を振り返ったうえで、それを補強するようないくつかのシェリングのことばを読解する。そこでは、シェリングが若き日にヘーゲルへと宛てた手紙のなかにある「思考の自由Denkfreiheit」という言葉に注目することで、シェリングにとって「思考」が、閉塞した現状のなかに「いまだ―なきもの das Noch-Nicht」へといたる「道」を見出すための「理性の冒険」であったことが示される。
このようにして導き出されるシェリング哲学の特徴は、「反政治」ということばによって特徴づけられる。ここでいう「反政治」とは、単に政治に無関心であるという意味の「非政治的unpolitisch」とは区別されており、法や国家による支配が人間生活に浸透していくことを積極的に「制限」しようとする積極的な姿勢のことを意味している。そしてその抵抗のためにシェリングが掲げたのが「哲学と宗教」である、というのが本稿において示さんとする視座である。すなわち、シェリングにとっての「(反)政治」とは、一般的な意味での政治—人々のあいだの利害や信条の対立—が人間の生を支配しないように、哲学と宗教によってそれを抑制するという、より高次の意味での政治、いわば〈政治に支配されないための政治〉だといえるだろう。