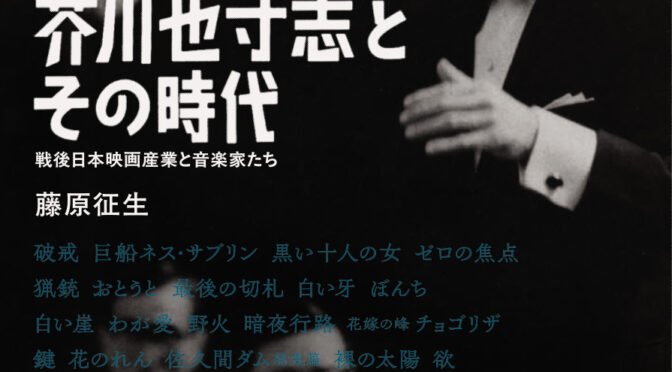衛藤 恵理香『『常陸国風土記』の表現と方法―地名と歌謡』
2023.05.15
衛藤 恵理香『『常陸国風土記』の表現と方法―地名と歌謡』
著者:衛藤 恵理香
日本文理大学経営経済学部助教
2017年京都大学大学院人間・環境学研究科共生文明学専攻博士後期課程修了
出版社:和泉書院
発行年月日:2023年3月20日
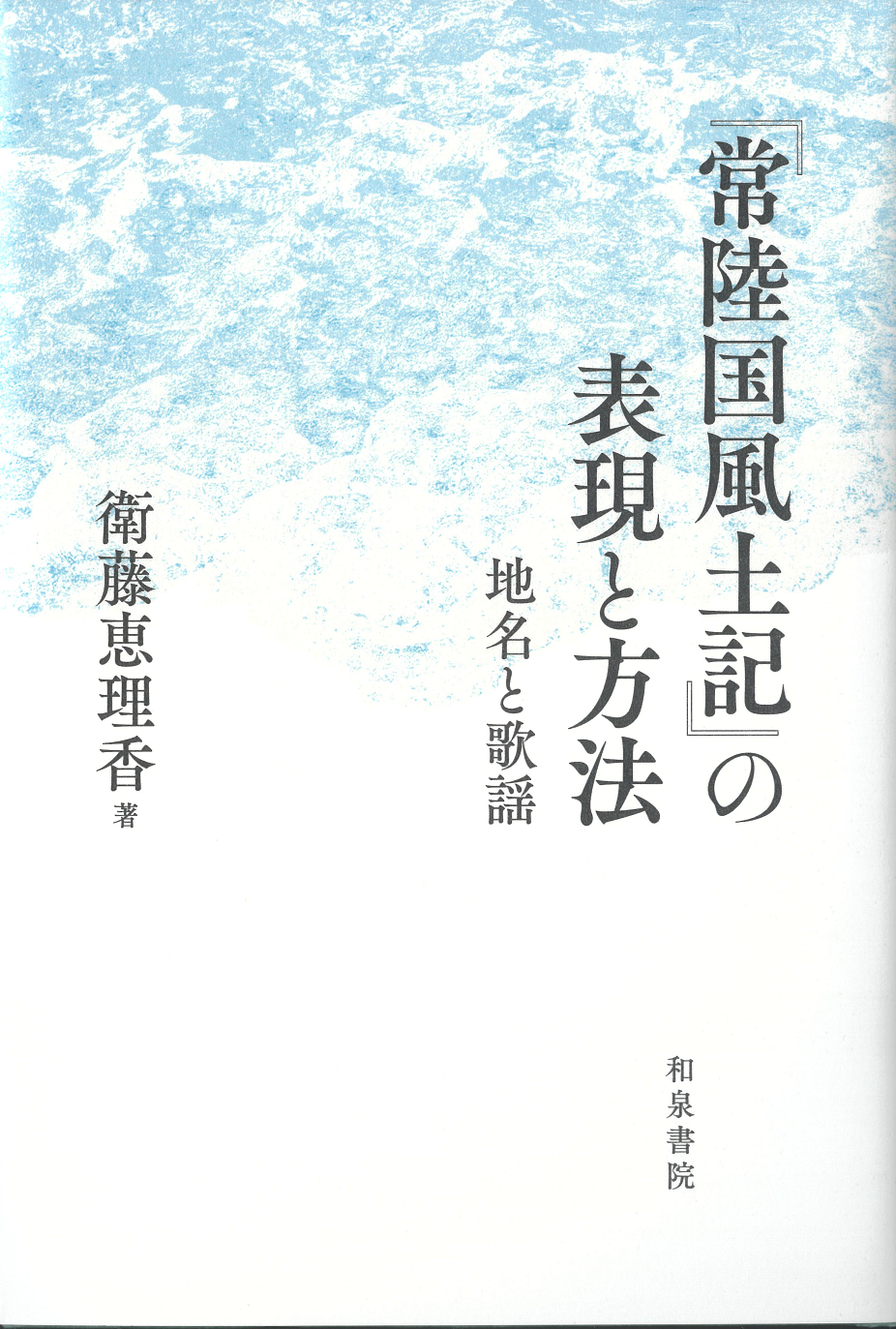
書籍紹介
『風土記』において歌謡はいかなる意味をもち、いかなる現れをしたのか
古代の人々における世界の把握のあり方と表現性への探究
《夏の口笛―浜辺》
例えば『常陸国風土記』茨城郡高浜条には、次のような記事が載る。奈良時代の暑い夏の日、浜辺での「嘯」という1つの文字に着目して、『常陸国風土記』の述作の意図と方法を解析してみたい。

従来の諸注釈書において「嘯友」は、「トモヲヨビ」と訓まれ、「友を呼び」とは、つまり「友を呼んできて」と解釈され、「嘯」の主語は浜辺で遊び楽しむ村人たちと理解されてきた。
「嘯」の用法や意味からすると、この従来の訓み下し文や現代語訳、従来の解釈は果たして正しいのだろうか。
《中国文献での「嘯」》
奈良時代の日本文学の多くは、その当時、最先端の文化・文学であった中国文献をお手本にして、発展してきたという側面がある。ゆえに中国文献においてどのような用法・意味をもっていたか、まずは確認する。

中国文献における「嘯」の意義の変遷について、青木正児氏は、次のように指摘する。
楚において死者の魂を招くのに嘯、すなわち口笛を吹く風習があり、それと同様に道士などが亡霊を招くのに口笛を吹く方法があったという。その延長に神仙家や道家が嘯、口笛を吹くことが行われた。それゆえ魏晉の時代に神仙家、道家的に世俗を超越せんとする気分で嘯することが生まれ、「嘯」は、俗世を離れ超然とした気持ちを表す言葉へと変遷した(『中華名物考』「『嘯』の歴史と字義の変遷」春秋社、一九五七年)。
《夏の口笛―筑波山》
『萬葉集』には「検税使大伴卿、筑波山に登りし時の歌一首 并せて短歌」(巻九・一七五三番歌)に「嘯」が用いられている。
暑けくに 汗かきなけ 木の根取り 嘯き登り
従来、ここでの「嘯」は、フーフー息をつくこと、として「汗かきなけ」とともに登山の難儀さをいったものと理解されてきた。
しかし、内田賢徳氏は、中国文献での「嘯」の意味をふまえたうえで、一七五三番歌「嘯鳴」は、今まで言われてきたような、フーフー息をついた、夏の登山の難儀さをいったものではなく、口をすぼめて口笛を吹いたものであり、登山によって生じた俗世を離れて悠然たる気分を表したものであったと指摘された(內田賢德「風と口笛」『説話論集』巻六、清文堂、一九九七年)。
《口笛を吹いたのは誰?―中国文献における太守(長官)の口笛―》
「嘯」は風を呼ぶための口笛を吹く動作を意味していた。ゆえに『常陸国風土記』の「嘯友」は従来の「トモヲヨビ」と訓むのではなく、正しくは「トモトウソブキ」と訓み、友と一緒に風を招く口笛を吹くことを表したものと解釈するべきである。
では、友と一緒に口笛を吹いたのは、どのような人物だったのだろうか?
『後漢書』(巻五十七党錮伝)には「嘯」で太守(長官)が口笛を吹いたことが次のように記されている。

内容を要約すると次のようになる。汝南という都市の太守であった宗資という人物は、部下である范滂という人物に仕事を任せた。そして南陽という都市の太守(長官)であった成瑨という人物もまた、その部下である岑晊という人物に仕事を委任した。この二つの都市の人々は歌をつくった。「実質的な汝南太守は范孟博、本当の太守である宗資は署名をするだけ。実質的な南陽太守は岑公孝、本当の太守の弘農成瑨はただ座って吟をなすのみ」と言った。
ただし、これは長官の怠慢さを言ったものではなかった。長官は政務を部下に委任し、功績は部下のものとして、美名を誇ることがなく、優れた人物を信任する名声は広く知れ渡ったと高く評価されている。「坐嘯」は、太守自らは何もせず、信任による理想的な統治を表している。
ここから『常陸国風土記』での「嘯友」は、従来の「トモヲヨビ」と、友を呼び寄せてと解釈するのではなく、「トモトウソブキ」が正しく、友と一緒に風を招く口笛を吹くことを表している。口笛を吹く人物は、ここでは常陸国の地方長官であり、この土地の長官が風を呼んで口笛を吹くとき、理想的に治められている土地であることを表している。
《『風土記』の価値の再検討に向けて》
今から約1300年前の奈良時代に成立した日本最古の地誌とされる『風土記』は、土地の性質や産物、説話や歌謡など、魅力に満ちながらも、今なお難解な表現や顧みられなかった本文など、検討の余地を残している。本書では、風土記において歌謡はいかなる意味をもつのか、述作の意図と方法の解析に基づいて考える。
注釈史を丹念に読み説いたうえで、従来の解釈にとらわれず、読解と訓詁を通して本文校訂を再検証し、常陸国風土記の表現と方法を明らかにする。それは、古代の人々における世界の把握のあり方と表現性への探究であるとともに、その基底には、生活や経験、態度といった現実感があったはずであり、風土記の表現世界を媒介とした、それら、言うなれば「古代的リアリティ」を探るものである。
日本文理大学経営経済学部助教
衛藤 恵理香