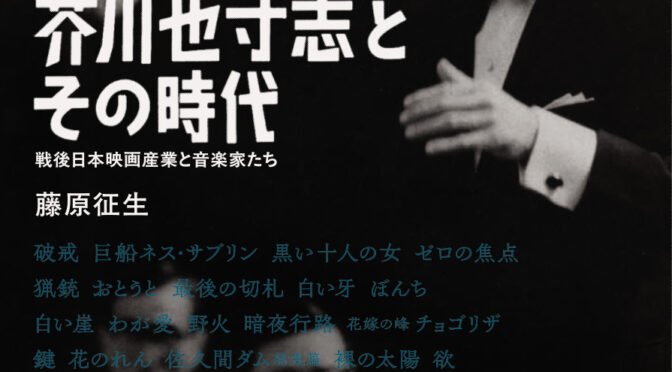中谷 森『シェイクスピアと日本語 言葉の交通』
2024.11.15
著者:中谷 森(津田塾大学学芸学部英語英文学科 専任講師)
出版社:春風社
発行年月日:2024年2月26日

書籍紹介
2016年に刊行された池澤夏樹編の日本文学全集第30巻『日本語のために』の第8章「現代語の語彙と文体」では、坪内逍遥・木下順二・福田恆存・小田島雄志・松岡和子・岡田利規ら6名による計7つの『ハムレット』第4独白の翻訳が並べて掲載されている。「一般の文体の変遷を辿るために」これらの『ハムレット』訳を集めたという池野の言葉が示す通り、明治以降の現代日本語の展開は、西洋の書物の翻訳、そしてより広くは物理的かつ精神的な西洋文化一般の輸入のプロセスと切っても切れない関係にある。
近代化の幕開け以来、日本人が吸収してきた種々雑多な外国の書物のなかでも、イギリス・ルネサンスをときめいた劇作家ウィリアム・シェイクスピアの戯曲が、現代日本語の文体の変遷を象徴するものとして、ここで取り上げられている事実は興味深い。「西洋化=近代化」という図式のなかで、シェイクスピアの戯曲、なかでも「生か死か」と悩んでみせる主人公ハムレットは、いわば近代性の権化として日本人の心のうちに特別な位置を占めるに至った。同時に、シェイクスピア作品が日本にもたらしたのは、近代や西洋という思想文化だけでなく、その特異な言語表現そのものでもあった。1882年発行の『新体詩抄』には、日本語になった『ハムレット』のうち最も早い例の一端として、‘To be, or not to be […]’と始まるハムレットの第4独白の翻訳が、外山正一と矢田部良吉それぞれの手によって収められている。外題が示す通り、『新体詩抄』の目的は、西洋詩からの触発を通じて日本語に新しい詩の文体を生み出すことであった。あるいは、川上音二郎による正劇『オセロー』の上演や、浄瑠璃翻案から逐次翻訳へと変遷した逍遥によるシェイクスピア戯曲翻訳の過程が示すように、旧劇とは異なる新しい劇言語を日本にもたらす上でも、シェイクスピアが担った役割は大きかった。
『新体詩抄』や、川上と逍遥の試みに明らかなように、明治期以降、シェイクスピアが日本語へと変貌していく過程は、シェイクスピア戯曲の受容を通じて新しい表現が日本語のうちに自然に派生していったという以上に、日本の作家や芸術家らによる意識的なプロジェクトとして、シェイクスピア戯曲を通じた日本語の実験と模索とが行われていったというべきものである。こうした視点を踏まえて、本書は、日本で制作されたシェイクスピア戯曲の翻訳および翻案作品のうち、とりわけその言語表現において実験的な試みを行った作品を取り上げ、シェイクスピア戯曲との関連において分析することで、従来の日本のシェイクスピア翻訳・翻案研究では看過されがちであった言葉と言葉の交通という観点から、シェイクスピア作品を取り巻く文化交渉の諸相を明らかにしようとした。
こうした本書の試みについて、その言語表現の巧みさによって知られるシェイクスピアの戯曲が日本語へと変貌する過程を研究するというのはいささか奇妙な試みとも思われるかもしれない。実際、シェイクスピアをめぐっては、その言語性こそシェイクスピア戯曲の本質であるとし、外国語であれ現代英語であれ異なる言葉に変えられてしまったのでは、それはもはやシェイクスピア戯曲ではない、といった言説がつきまとってきた。1990年代以降を中心に、シェイクスピア研究においてはこうした態度への見直しが図られ、今では外国語によるシェイクスピア上演や翻案作品の研究が盛んに行われるようになっている。しかし、こうした研究の多くは作品の視覚的要素や社会政治的な文脈に着目する傾向があり、他国語へと翻訳・翻案されたシェイクスピア作品の言語性に目を向ける研究は決して多くない。本書は、こうした研究の現状に一石を投じようとするものである。
本書で取り上げたのは、小林秀雄の翻案小説『おふえりや遺文』(1931年発表)、福田恆存による『ハムレット』の翻訳上演(1955年初演)、木下順二による『マクベス』の翻訳と改訳(1970年発表・1988年改訳)、そして平川祐弘作・宮城聰演出の『オセロー』の夢幻能翻案(2005年初演)の4作品である。本書は、これら4作品の検討を通じ、シェイクスピア作品の核心にあり、「シェイクスピア」という名の実体そのものとも呼べる「ことば」に焦点を当てることで、言語と言語の境界における越境と混淆のあり様と可能性とを考えようとするものである。