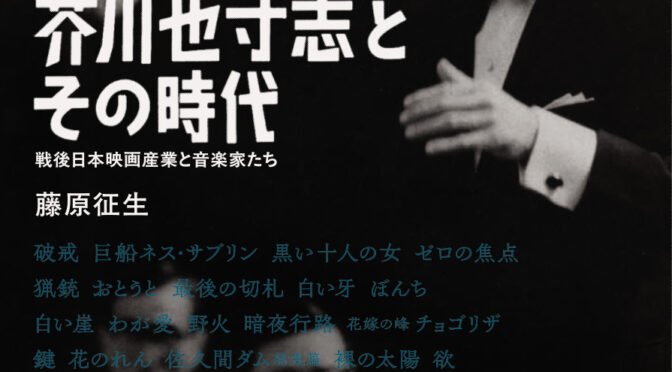比護 遥『近現代中国と読書の政治:読書規範の論争史』
2024.10.26
書籍紹介
本を足で踏みつける様子を、頭に思い浮かべてみてほしい。言いようもない嫌悪感を覚えるという人は少なくないだろう。書籍は一定の内容を伝達するためのメディアであるが、それだけに留まらない文化や文明そのものを象徴するものとなっている。それゆえ、読書する国民の多さは国の誇りとなるし、「読書離れ」の進行は危機として社会的に語られる。そして、本を破壊する行為は野蛮の極致として非難の対象となる。「本を焼く者は、やがて人を焼くようになる」――ハインリヒ・ハイネのこの警句は、今なお巷間に好んで引用される。
それでは、本を読みさえすれば何でもいいのだろうか?例えば、20世紀最大のベストセラーは間違いなく『毛沢東語録』であるが、これが全国民に熱心に読まれた文化大革命期の中国は、この上なく文明的だったのだろうか?当時の状況を詳しく知る人ほど、それは違う、と言いたくなるかもしれない。そう感じるのは、もともと私たちのなかに読書が「かくあるべき」という想定があるからだ。例えば、目先の利害にとらわれず、じっくりと思考しながら読むのが望ましい。それゆえに、政治的スローガンをただ繰り返すだけのようなものは、読書の名に値しない、というように。
ただ、私たちが現在「あるべき読書」と考えているものは、決して無条件に成り立っているわけではない。時や場所が変われば、「あるべき読書」も変わる。博士論文をもとに出版した『近現代中国と読書の政治:読書規範の論争史』において、私はこれを「読書規範」と呼び、20世紀中国におけるその変遷を辿った。
中国において、近代に入るまで、何が「あるべき読書」なのかというのはほとんど自明のことであった。それは官僚登用試験としての科挙制度があり、儒教的教養の保持者としての「読書人」が支配階級となっていたためである。したがって、読むべきものとされたのはまずもって四書五経であり、儒教の聖典を通した修養が、最終的に国の安定につながると期待された。もっとも、科挙での成功は宗族を支えるほどの経済的利益を約束するものであるがために、その読書の内容における教養重視の性格にかかわらず、受験者個人にとっては読書がきわめて実利的な意味を持っていたことにも留意が必要である。すなわち、読書の目的において、人格の修養という「建前」と、立身出世という「本音」を、経典を科目とする官僚登用試験によって両立させていた。この絶妙なバランスは、近代になってから、崩れることになる。
20世紀の中国において、さまざまな雑誌や新聞において、何が「あるべき読書」なのかということが盛んに論じられた。読書規範が議論の的となるのは、それが定まっていないことの裏返しでもある。機械化された活版印刷の技術的後押しもあり、出版点数は大幅に増加した。西洋諸国に比べれば識字率がかなり低かったものの、限られたエリート層ではない読者も多く現れた。本をどのように選び、どう読めばいいのかという共通認識はもはやなくなる。そもそも、言論を交わす雑誌や新聞といったメディア空間そのものが広まったことも重要である。とりわけ1930年代には、書評や読書指導を専門的に行う「読書雑誌」も相次いで発行された。本書で用いた資料の多くは、その後も時代とともに形を変えつつ発行が続いていった読書雑誌の数々である。
読書を論じる膨大な言説を整理するために、本書では特に「論争」に焦点を当てた。異なる意見がぶつかり合う論争の文脈から、論点の所在を明確にできると考えたためである。本書で見出した対立軸はさまざまにあるが、なかでも重要なのは時間感覚に関わるものである。すなわち、読書はすぐに何かに役立てるためのものなのか、それとも長期的に知識や教養を身につけていくためのものなのか、というものだ。この問いが大きな意味を持つのは、書籍というメディアそのものの特性に由来する矛盾と関わるためである。ラジオや映画、テレビなどといった20世紀の「ニューメディア」と比べて、書籍は決して効率的なメディアとは言えない。その一方、相次ぐ戦争と革命を経験したこの時代の中国は、時間的な余裕が乏しかった。それならば、それでもなお読書すべき理由は何であろうか(あるいは、そもそも読書すべきではないのだろうか)?
読書というのはほとんどの人に経験のある行為であり、しかしそれは単に個人的なものに留まることはなく、ときに社会や政治と密接に結びつく。私は本書において、上からの中国政治史を描くのではなく、ごく身近なところから中国社会のダイナミズムを感じてもらおうと試みた。
そして、狙いはもう一つある。それは私たちの「現在地」を見直すことである。読書の歴史にとって、中国は確かに特異なケースであるが、しかしそこには多くの普遍的な問題も含まれている。私たちは今、インターネットというこれまで以上に加速したメディアに取り囲まれ、日々時間に追われた生活をしている。書籍は決して力のあるメディアとは言いにくい現状であるが、今後はどうだろうか?どのような文化の形を思い描いていけるであろうか?考えるための一つの材料に、本書がなれば嬉しい。