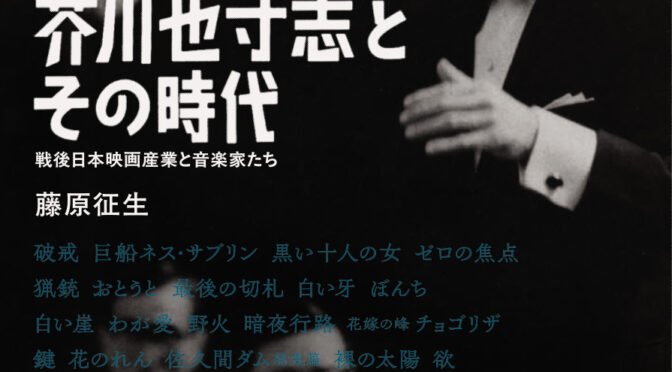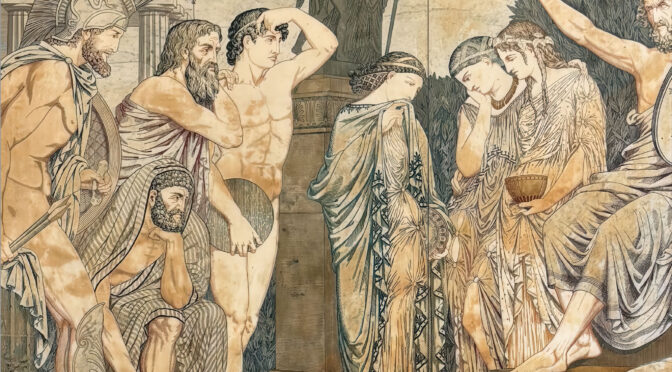福元 健之『医師の「献身」:ポーランド建国と草の根知識人 1890-1920』
2024.10.21
書籍紹介
研究者を志す同世代の仲間との切磋琢磨を求めて京都大学大学院の門を叩いてから、あっという間に12年が過ぎた。本書のテーマは、博士後期課程に在籍中、ポーランドに留学したことをきっかけに本格的に取り組んだもので、指導教員とも、友人たちともまったく違った対象に関する研究であったが、調査のための知的能力が試されたその時々で、大学院演習や研究会の場で積み重ねられたものを実感した。その意味で、非才ゆえに日々の努力は惜しまなかったつもりだが、日本の西洋史学の教育環境(大学に留まらない!)があってはじめてこの本は生まれたといえる。
刊行にあたっては、私自身の20代から30代前半までの活動の集大成となるとあって、スケジュールぎりぎりまで手を加え続けた。正直このままずっと校正を続けたい、と思わなくもなかった。といって、実は、出版までの一年間、内容に関しては、ほとんど何もいじっていない。では何をしていたのかというと、それは、本の可読性を改善する作業で、タイトルから、写真やコラムの配置、帯文のことまで、商品としての本の価値を少しでも上げるようにした。
19世紀末から20世紀初頭のポーランドの医師のことなど、日本で知っている人はほぼ皆無のため、本書では写真を多く配置するようにした。これらは、なじみのない議論ではあっても、ある程度のイメージをもって読んでもらえたらとの思いからだが、実は、本書で利用した写真のほとんどは、パブリックドメインに分類されており、ポーランドの文書館のウェブサイトで公開されている。したがって、素材自体はその気になれば誰にでも見つけられるものであって、写真の利用自体に独自性があるわけではない。しかし、その写真をめぐる文脈や事実に関する知識を通じて、そうした視覚的素材にどのような意味があるのかを解釈し、議論の中に位置づけた行為には、私自身の創意工夫がある。その意味で、史料のオリジナルさが求められる歴史学に対して、写真に関しては、本書はささやかな反抗をした。
また、本の書き出しについても、あまり従来では見られないことをしてみた。あまり詳細は書かないようにするが、これも読者の想像力を揺さぶるための仕掛けで、もし自分が当時の世界にいたらどのようなことを経験するかを、これまでの研究を通じて得られた知識に基づいて物語風に書いてみた。フランスの歴史家イヴァン・ジャブロンカの著作『歴史は現代文学である』(真野倫平訳、名古屋大学出版会)に触発されて、研究者仲間と論稿を書いたりしたのに、自分で何も実験しないのは二重基準になってしまうと考えたことも背景にある。ただ、ある尊敬する日曜歴史家からその部分は評価してもらえたが、書き出しの文章と、それ以降の文章との調子の違いを指摘されてしまった。それゆえに、結局のところ、博士論文を基にしている本書は、形式や慣例に忠実な学位論文の枠組を抜けだせていないのかもしれない。
京都大学学術出版会のプリミエ・コレクションの一冊に加えてもらった本書だが、偶然にも私の「初演(プリミエ)」、すなわち最初の単著は、群像社から刊行されているポーランド史叢書の一冊として刊行された(『王のいない共和国の誕生』)。これは、ポーランドでは専門家なら必ず知っている知識や史料に基づきつつも、通説とは異なる歴史像の提示を試みたものである。「共和国に王がいないなんて当たり前じゃないか」と思われるかもしれないが、近世のポーランド=リトアニア「共和国」に王は存在したし、19世紀を通じて、いや第一次世界大戦期においても、立憲君主国としてのポーランドの構想は根強かった。にもかかわらず、なぜ、近代的な共和国としてポーランドは独立したのかを、本書では論じた。ポーランド史叢書の目的が、日本の読者になじみのないポーランドの歴史を分かりやすく伝えることであったこともあり、そこでは概念の規定や、先行研究の整理など、学術的な手続きは楽屋に控えるだけで、出番はなかった。本書では、それらを前提に物語ることができたのである。
本書も、こうした軽やかさをもって書くことができたらもっとよかったのかもしれない。本書を一貫する筋書き自体は、地方医師から自治体の医師への変化と一言でもまとめられる。ただし、その内実は、実際に複雑であった。私は、本書で、ワルシャワという中心の外にいる「地方」のための医療を模索していた医師たちが、第一次世界大戦を経て、新生ポーランド国家の基礎としての自治体で勤務するようになるまでの歴史を書いた。注意したいのは、現代の私たちとは違って、医師たちは1918年にポーランド共和国が再建されることを知っていたわけではない。ある時期までのかれらは、ロシアやドイツによる支配を前提に行動し、やがて独立ポーランドを支えるようになった。紆余曲折をたどる医師たちの活動を実際に貫徹したのは、目の前の患者の病気を治すことだった。とりわけ、子どもは貧困や不衛生の犠牲者と認識され、介入の対象となり、児童保護を通じて、自治体における医師の地位は確立されていったといえる。
医学部を出ていない身で医師の歴史を論じることには、いつも後ろめたいところがある。ゆえに、私は、自分の研究で、社会のなかで医師はどのような役割を果たしたのか、あるいは、医師は社会とどのように関わろうとしたのか、を追求してきた。本書の主人公であるユダヤ人医師のセヴェーリン・ステルリングが結核対策の専門家であったことから、そのテーマについては医学史的にも意味があることを書けたのではと期待するが、その判断も読者に委ねるほかない。いまはより多くのひとに、社会に献身しようとしたポーランドの医師たちについて読み、知ってもらえるように祈るばかりである。