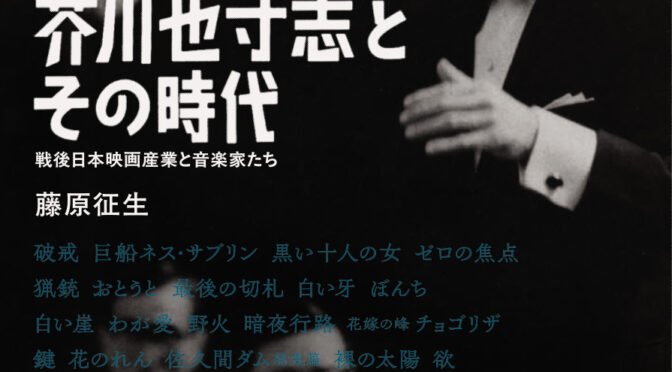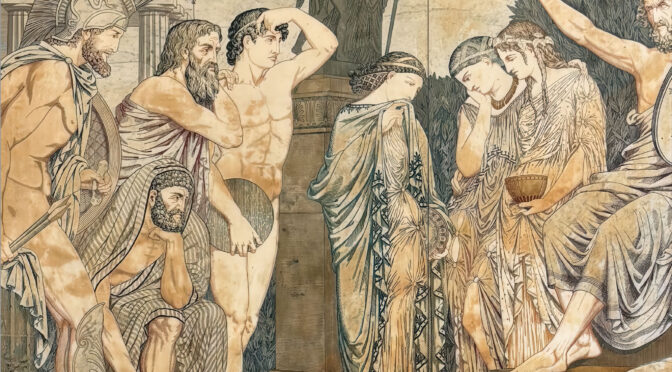髙谷 掌子『「私と汝」の教育人間学――西田哲学への往還――』
2024.10.21
書籍紹介
本書の背景となる問題意識として、「夢」に対するアンビバレントな心性がある。
「夢」というのは、たとえば、学生生活の始まりに抱くようなものである。大学図書館に初めて入ったとき、そこに並ぶ無数の専門書を見て、これから好きなだけ読むことができるだろうと期待する。受験勉強のプレッシャーもない。大学生には時間があるという。この棚の本も、あの書庫の本も、いつか読めるだろうという夢を見る。
だが、実際には、自分で読むことのできる本はほんのわずかである。学生生活は勉強だけではないのだ。そう自分に言い聞かせて、読みさしの本を返却する。学年が上がるにつれ、特定の図書室の特定の書架の本にお世話になることが増えていく。自分の好きなように、どこまでも手を伸ばすことができるだろうというあの予感は、「夢」に過ぎなかったのか。
図書館の本だけではない。受験生のときに抱いていた学生生活への期待、親元を離れて自活してみたいという期待、もっといえば、子どもの頃に抱いていた「大きくなったら…」という期待は、果たして叶えられたといえるのか。もし、それらが全面的に叶えられたとはいえないのだとしたら、子どもに向かって「頑張ればできるよ」、「大きくなったらできるよ」と声をかけることは、大人として不誠実ではないか。まして、「夢を叶えたいなら、今は我慢しなくちゃね」という仕方で未来への期待を高めることは、現在を犠牲にすることではないか。とはいえ、「そんなものはただの夢で、叶うわけないよ」と否定することもまた、大人の独りよがりではないか。
要するに、子どもの「夢」を肯定し応援したくなる心性と、それによって現在を犠牲にすることへのためらいとの間で、私たちはどのような態度をとるべきか。本書はそのような問題意識を背景として書かれた。
そのような問いを原動力として、本書は、戦前の哲学者・西田幾多郎と、戦後の教育学者・森昭との間に、時代を越えて交わされうる対話を仮構することを試みる。西田は、明治の初めに生まれ、西洋の哲学と東洋の思想が交じり合うところで思索したことで知られている。しかし、西田の言う「絶対無の自覚」は、もはや哲学ではなく一種の宗教的境地を言い述べたに過ぎないのではないかという批判が、西田の同僚の田邊元から提起された。そのことをきっかけとして、この二人を中心とする哲学者ネットワークに「京都学派」という名が付けられた。他方、森は、田邊に学びながらも、戦後は京都学派との関連を表立って主張することなく、「人間生成」としての教育人間学の構築に取り組んでいく。その核心には、哲学者が主張するような「自覚」もまた「人間生成」の可能性の一つとして、やはり「生成」するものであることを看過してはならないという信念があった。
本書の見立てでは、西田の「絶対無の自覚」は、京都学派の間で一種の「夢」として作用したのではないかと考える。西田にとっては、自覚は自ら覚る事実であって、夢に見る対象ではない。しかし、それは、西田の自覚論を読む田邊や弟子たちにとっては、彼ら自身が日常的に体験している事実であるとは思われない。それゆえ、西田のように考究を続けていけば、いつか「絶対無の自覚」に到達できるかもしれないという「夢」が生じてしまう。森が主張したのは、教育人間学はそのような「夢」の内容そのものを語るのではなく、人間は「いかにして」夢の先へ至るほどに「生成」するかを明らかにすべきであるということである。この角度からの批判に対して、西田の応答を「私と汝」論における〈自覚の始まり〉に読み取ることが、本書の中心課題である。
冷戦期構造の崩壊以降、日本の戦後教育学が勢いを失い、ポストモダン教育学が模索される中で、本書が論じる教育人間学という分野は、事象の個別性に立脚した教育学として改めて注目を集めている。とりわけ京都学派の哲学と教育人間学の関わりについては、京都学派へのイデオロギー的批判が冷静に再考され、日本哲学の国際化が進められる中で、およそ2010年代以降の日本の教育哲学・教育思想史研究において再評価が進められている。
本書はこうした研究動向を引き受けながら、教育人間学の理論面について、その源流にある京都学派の哲学に遡って再構築を行うとともに、歴史上は師弟関係になかった西田と森の間に対話を仮構していくところにオリジナリティをもつ。それは、日本の戦前と戦後、哲学と教育学の境を越えて対話するための試みである。教育に関心をもつ読者には、西田哲学への往還を、西田哲学に関心をもつ読者には、教育人間学への越境を楽しんでいただければ幸いである。