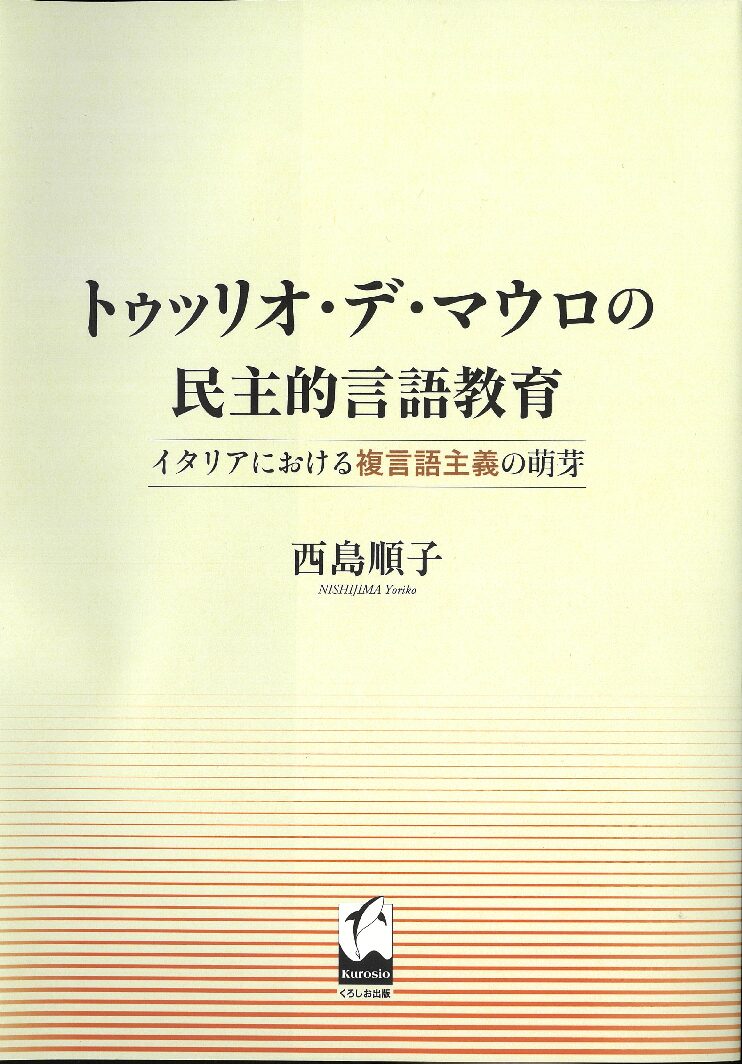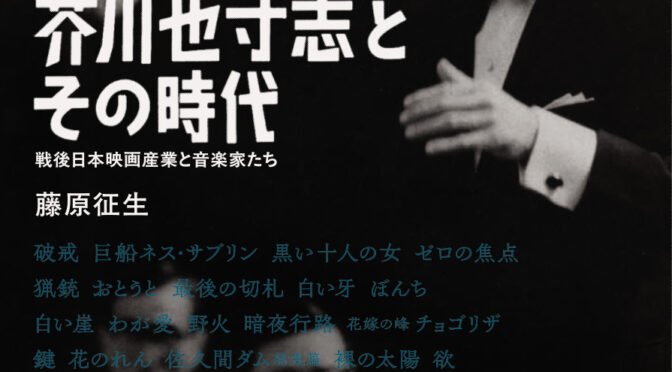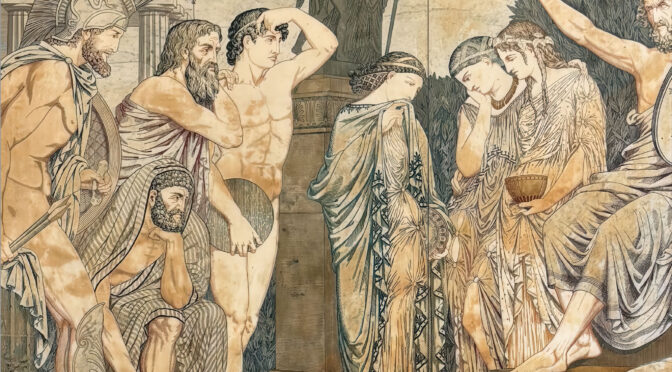西島 順子『トゥッリオ・デ・マウロの民主的言語教育-イタリアにおける複言語主義の萌芽―』
2024.10.19
著者:西島 順子(大分大学 教育マネジメント機構国際教育推進センター 講師)
出版社:くろしお出版
発行年月日:2024年2月9日
書籍紹介
地球上には5000もの言語が存在するともいわれているが、それら言語に覇権が存在することは想像に難くないだろう。グローバルな視点で考えれば、英語の世界的な普及はもはや抗えない事実であり、日本という地域で考えれば、日本語の圧倒的な支配力は他の言語の存在をも埋没させる。しかしそれら覇者の陰には、その他の言語話者である弱者が存在することを忘れてはならない。
ヨーロッパにも多様な言語が存在するが、欧州評議会は言語教育政策に関して、各国の言語、あるいは各地の少数言語の平等性を担保するため、複言語主義を選択した。それによって欧州域内では現在、イデオロギー上、すべての言語に対する尊厳が保たれ、またEU市民には母語以外の言語の習得が推奨されている。この複言語主義が提唱されたのは2001年であるが、実はそれより20年以上も前にイタリアにおいて複言語主義に類似する「民主的言語教育」と称する言語教育改革が提言されていたのである。
この民主的言語教育とは、言語学者トゥッリオ・デ・マウロが中心となって構想した言語教育思想である。1975年に10のテーゼとして発表されたその宣言には、デ・マウロのplurilinguismo(複言語主義)の概念が包摂され、生徒の言語的出自の多様性を発見し尊重することや、 生徒がすでに所有している方言や少数言語などの能力を承認することなどが示された。
イタリアがこのような教育改革を必要としたのは、学校教育における深刻な問題があったからだ。イタリアはそもそも地理的、歴史的理由から、個別言語ほど異なる言語変種や少数言語が数多く共存する国である。しかし、1861年の国家統一以降、フィレンツェ語、つまり今でいうところのイタリア語による単一言語教育が推進され、言語の多様性は一貫して否定され、規制された。ただ、この一世紀にわたる言語政策、また言語教育政策はイタリアの複層的な言語状況を根本的に変容すること、つまり単一言語の普及を徹底し得ることはなかったのである。それゆえイタリア統一から100年を過ぎた1960年頃もなお、方言話者や少数言語話者はイタリア語の無理解により、公教育からドロップアウトし、義務教育を十分享受できないまま社会的弱者となっていた。デ・マウロはこの事実を看破し、単一言語教育でその格差を是正することはできないと確信し、plurilinguismoに基づく民主的言語教育を構想、提言するに至るのである。
本書は、イタリアのplurilinguismoとデ・マウロの思想を中心に、1960年代から1980年代までの民主的言語教育の始まりとその展開を詳らかにした。第一章では近現代イタリアにおける言語状況と言語政策の展開、第二章ではイタリアにおけるplurilinguismoの歴史的変遷、第三章ではトゥッリオ・デ・マウロの構想したplurilinguismo、第四章では民主的言語教育における複言語教育の実践、結論として民主的言語教育の教育的意義について論じた。
民主的言語教育は今から50年前の言語教育の思想であるが、現代の文脈に置き換えても決して意義を失っていない。今も力強く存在し続ける方言や少数言語、また移民がもたらす言語は我々の言語環境を以前にもまして一層豊かにしている。しかしながら、そこにはやはり言語的弱者が存在し続けている。そういった声なき者たちに耳を傾ける社会や教育を考えるとき、この民主的言語教育は一つの道しるべとなってくれるのである。