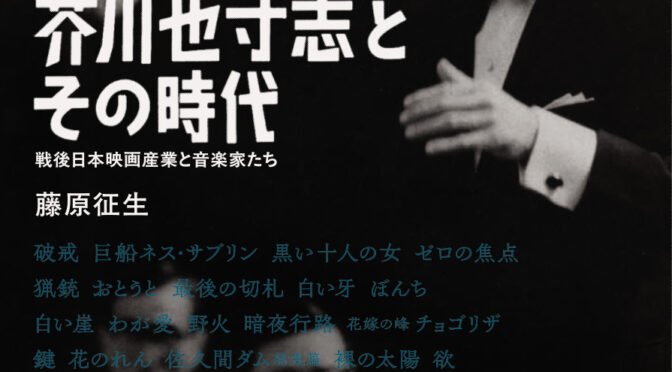王 令薇『《中学生日記》のメディア史:自主性を演じるドラマ』
2024.09.27
著者:王 令薇(江戸川大学助教)
出版社:創元社
発行年月日:2024年2月14日

書籍紹介
先日の土曜日の夜、私は目黒シネマで『14歳の栞』という映画を見た。この映画は、埼玉県のある公立中学校に通っている35人の少年少女の日常に密着したドキュメンタリーである。『中学生日記』について研究している人は『14歳の栞』も見てみるといいかもしれないと、勤務先の映画監督の先生に勧められ、その存在を知った。関東の映画館で上映されているのをたまたま見つけ、目黒まで足を運んだ。35人の生徒の生の声と特別感のない日常だけを題材としたものであり、主人公も起承転結もないにもかかわらず、レイトショーは補助席まで満席になるほどの人気であった。
本書の対象であるNHK名古屋放送局制作の長寿ドラマ『中学生日記』の魅力も、まさに思春期を迎えた中学生たちの「ありのままの日常」を描き出す点にある。ただ、『14歳の栞』と異なり、ドキュメンタリー形式では捉えきれない中学生の「本音」に迫るべく、『中学生日記』はあえてドラマ形式、言い換えれば、フィクションを採用した。つまり、ディレクターたちが事前にインタビューやアンケートで中学生の「本音」を集め、その結果をもとに脚本家が台本を作り、生徒たちが与えられた役を演じるスタイルであった。1970年代から2010年代にかけて、『中学生日記』がこうして提示した「リアル」とその「中学生の目線に寄り添った」一貫した姿勢は、多くの視聴者を惹きつけた。
しかしながら、言うまでもなく、これらの映像作品に映った「ありのままの日常」は無色透明のものではなかった。また、そうあるべきだとも思わない。現に、『中学生日記』を「テーマをストレートに出せる、自分の思いを重ねることができる」番組であると振り返るディレクターもいる。では、この「ありのままの日常」にどのような制作者の思いが隠されているのか。視聴者は番組に何を求めているのか。時代とともにストーリーがどのように変化してきたのか。出演者の中学生に対していかなる影響を与えていたのか。これらの問いについて探り、考え、『中学生日記』が提示した「リアル」の内実と役割を明らかにすることが本書の目的である。
現実とも虚構ともつかないこの「中学生のリアル」を、私は「演出された裏領域」として捉えている。この観点から、≪中学生日記≫のフレームは、1970年代の放送開始当時は競争社会や管理社会などの広範な社会問題に焦点を当てていたが、1980年代半ば以降、保護者もしくは教師の個人責任を強調する方向へ変わっていることがわかった。そして、2003年度以降の同番組では、恋や友情、思春期の体と心の変化による悩みが前景化し、生徒たちは、大人に反抗する中学生ではなく、能動的に社会での自立をめざす個人として描かれるようになった。加えて、2000年代においてインターネット並びにSNSが普及したことで、生徒の日常が「上演」される場所は学校・家庭からオンライン空間へと移行し、「中学生のリアル」が見えにくくなり、「大人」の眼差しも後退した。こういったメディア環境の変動に同番組終了の最大の要因を求められると本書で論じている。
『中学生日記』のメディア史的研究は、私自身の研究者人生の出発点としても位置づけられるため、この一冊では十分に答えられなかった問題がいくつかある。ここでは、すべてには言及しないが、現在取り組んでいる研究テーマとの関連で二点を書き留めておきたい。
第一に、中学生がどのように見られているかについてである。前述の映画『14歳の栞』の企画だけではなく、「少年の主張」という中学生イベントの継続、中学生が主人公のマンガ『君たちはどう生きるか』やノンフィクション『僕はイエローでホワイトでちょっとブルー』の商業的な成功が示しているように、「中学生」に意味を見出そうとする大人の試みが2020年代において終焉を迎えたわけではない。私は、子供と大人との境界線が曖昧であり、「成長」や「反抗」を描き出すことが困難であるこの時代における「中学生」イメージのあり様とその変容について検討し続けたいと考える。
第二に、「普通の人」「日常」の映像文化論の可能性である。「普通の人」や「平凡な日常」が視聴者の関心を集める現象は、動画共有プラットフォームでよく見られるものであり、とりわけブイログ(Vlog)と呼ばれる動画では、この傾向が顕著に現れている。また、2000年代以降のテレビにおいても、NHKの『ドキュメント72時間』(2006~7、2012~)やテレビ東京の『家、ついて行ってイイですか』(2014~)などのドキュメンタリーの手法を駆使して「普通の人の日常生活」を切り取ろうとする番組が話題を呼んだ。こうした「日常」をめぐる、見る側と演じる側の不均衡な関係性とその影響に着目していくことが、「中学生のリアル」に関する本書の議論が導くもう一つの課題であろう。本書がテレビ研究者・映像研究者・教育メディア研究者にとってはもちろんのこと、日本の中学校教育の変容に関心を持つ方にとっても少しでも参考になれば幸いである。