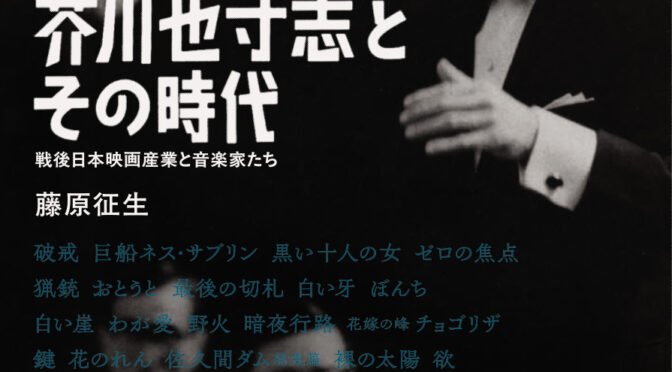福田 安佐子『ゾンビの美学:植民地主義・ジェンダー・ポストヒューマン』
2024.11.20
著者:福田 安佐子(国際ファッション専門職大学 助教)
出版社:人文書院
発行年月日:2024年3月30日
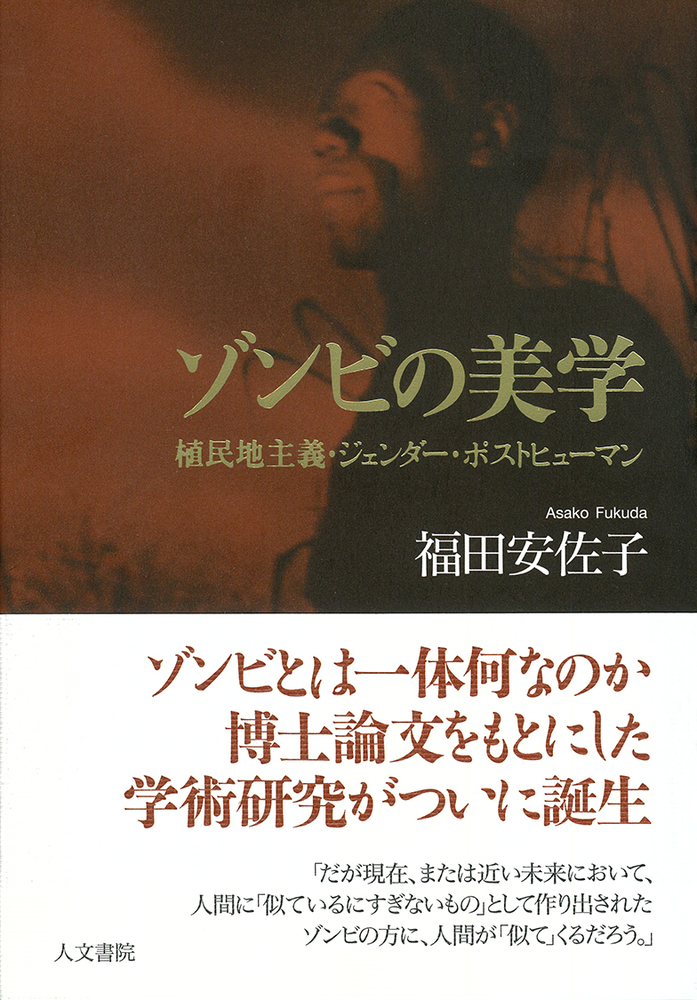
書籍紹介
「ホラー映画がお好きなんですね」とこの研究を始めてからよく聞かれるようになった。また、大学でゾンビについての講義をしていると、ハロウィンの日はゾンビの格好で授業にやってくるだろうと、学生に期待されていたりもする。本音を言うと、ホラーは怖くて苦手であったし、仮装して授業をするほど陽気なキャラクターではないので、こういった場面に遭遇すると、当然戸惑いを覚える。とはいえ、あくまで研究対象なのだ、とゾンビに対して距離を持って付き合っているわけではない。私のなかでは、ゾンビを研究することとこの戸惑いは全く矛盾していないのだ。というのも、ゾンビ映画やホラー映画を見ればみるほど、両者の「怖さ」は別のところにある、ということがわかってきたし、ゾンビの「見た目」にじっくり向き合い、特殊メイクの変遷や時代ごとの影響について考えてきたからこそ、「ハロウィンにふさわしいゾンビの格好とは?」と考え込んでしまうからだ。
しかしまた、冒頭のような言葉が全くの予想外、ということでもない。そもそも「ゾンビ」を研究しようと思ったきっかけには、ゾンビのもつそのキャッチーさがある。誰もが、ゾンビといえばこういうものだろう、と一定のイメージを持っているのであり、言い換えれば、「知っているけれど、よくは知らない」という絶妙な立ち位置にゾンビはいる。私が初めてゾンビ映画を観た時もそうだった。それまでゾンビ映画の鑑賞経験はなく、レンタルビデオ店のポップでオススメされたものを手にとった。どす黒い顔色か、血塗れか、または緑色になった肢体を引きずって、ノロノロとこっちへ向かって歩いてくるもの。さらに、なぜか生きている人間だけを選り分けて、生きた肉に食らいつこうとする。集団で襲いかかってくるのだが、逃げ切ることができそうな速さでもあるところにスリルがある。そして、逃げ切れたとしても、噛み跡がつくか傷口にゾンビの体液が触れてしまえば、そのうちその人もゾンビになってしまう。そういったゾンビ映画にある「ルール」を、私はその映画を見る前から、なぜか知っている。この「事前に知っている感覚」はなんだろう、という衝撃が本書の出版に至るまで続いた、と言っても過言ではないだろう。
ゾンビのイメージのそこ知れぬ力には、研究を初めてから十年強のあいだ、何度も驚かされることになる。研究者同士の自己紹介では、「専門はゾンビ」ですと言えばそれだけで通じる。もちろん世界中の人に対してそうである。相手がどんなに気難しそうな高齢の学者であっても、ヤンチャそうな子供であってもだ。翻訳の必要もなく、「ゾンビ」というこの三文字は、最もユニバーサルな用語ではないかと思ってしまうほどである。
さて、研究を進めるにつれ、ゾンビがいかに奥深く、そして興味深い歴史を背負ったものであるか、ということもわかってきた。自分が生きている世界を形作っている近現代の様々な事象に、ゾンビはそれぞれの仕方で関係しているのである。例えば、「蘇った死体」としてのゾンビが生まれたのは、1930年前後のハイチであるとされるのだが、それには植民地主義や奴隷貿易が関係している。すなわち、ハイチへとつれてこられたアフリカの人々が有していた土俗宗教と、宗主国である西欧のキリスト教とが融合して出来たヴードゥー教というものの存在があり、それが象徴する奴隷反乱への脅威や、または純粋な好奇心が、プランテーションで酷使されるゾンビ像を生み出した。このように最初のゾンビ(本書で「クラシック・ゾンビ」と呼ぶもの)は、植民地主義を背景としているのだが、それがなぜアメリカにおいて「モンスター映画」として題材になったのかと言えば、アメリカが西欧諸国から遅れて植民地主義に乗り出していたこと、さらにはトーキー映画の登場によってモンスターの活躍する映画が流行したことや、不況の影響といった映画の歴史も関わってくる。またはその白黒の画面やCGなどがない時代にどうやっておどろおどろしいモンスターたちを描いたのだろう、という興味も湧いてくる。一方で、そのもととなったアフリカでの「ゾンビ」が何を指していたのかを調べてみれば、精霊や幽霊のようなもっと普遍的なものが出てくる。小泉八雲の名で知られるラフカディオ・ハーンが著したマルティニーク諸島に滞在していた頃の書物には黒人乳母が「早く寝ないとゾンビがやってくるよ」と小さな子供を寝かしつけている。ゾンビを鬼に入れ替えれば、昔どこかで聞いたような文句であろう。
ゾンビがこのように、ある時代に特殊な条件にも、普遍的なものにも関連しているのは、1930年代だけに限ったことではない。1960年代の人を食べるようになったものや、2002年以降の走って追いかけてくる凶暴なものもそうである。それはなぜ、どのようになされてきたのだろうか。ゾンビとは、やはり「死」という、全ての人間にとって逃れられずしかし誰もが必ず一度は経験するものでありながら、日常において実感することが稀で、生活から隔てられているものに、最も近いものだからだろうか。しかし死や人間というものの尺度も、よく考えてみればひどく曖昧なものである。しかしだからこそ、興味や研究は尽きないのである。とりあえずこの100年のあいだ、そのちょっと恐ろしく、そしてちょっとコミカルなものとして想像され、誰もが知ることとなった「ゾンビ」にこだわって考えてみよう、というのが本書の目論見である。